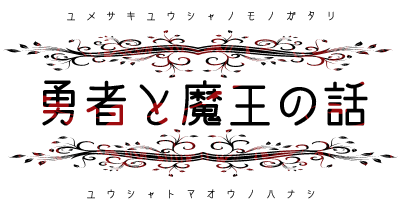昔ある世界で魔王が生まれました。
そして勇者も生まれました。
勇者は魔王を倒しました。
それでめでたしめでたし――――になったのでしょうか?
「殺すがいい」
そう、くぐもった声が聞こえてきた。
黒いマントに覆い隠された顔の辺りからだった。
「なん……だって?」
チャキ、と剣を構えた。その言葉がよくわからなかったからだ。
「殺せ、と言っているのだ」
やはりくぐもった声。
両手を広げてもう一度同じ言葉を繰り返した。
冗談ではない。
「何を言っているのだ、魔王!!何を考えている!!」
再び剣を構えて間合いを十分に取った。こんな言葉に惑わされるわけにはいかないのだ。
だが魔王は最早戦闘の意思など無いかのように持っていた杖を放り投げる。
そして顔までを覆っていたマントを剥ぎ取った。
現れたのは見目麗しい青年だった。
年の頃は私と同じか、少し上か。
ブロンドに赤い瞳。鎧をつけたその姿はまるでどこかの騎士のようで。
しかし普通と違うのは首に入った線。
無理に縫い合わされたような痛々しいジグザグ模様。壊死しているかのように黒く変色している。
その傷に魔王が触れて言った。
「全てを思い出した」
マント越しではない声はよく通り、どこか悲しげな音色で響いた。
「僕がどうしてこんな所に居るのかも、どうしてこんな事をしているのかも、そしてこの首の傷の理由も」
ぐちゅ
傷に沿って無理やり指を入れていく。プツプツという音と共に縫いとめられていた糸が切れ、首は離れていった。
「なっ、何をしているんだ?!」
気味の悪い光景と、それに似合わない優しげな表情。
そして何より、黒マントの下が自分達と変わらない“ヒト”だったという事に対しての動揺が私を包んでいた。
魔物をいくら切っても、魔王と対峙しても震えなかった腕が僅かに揺れた。
“彼”はそんな私を見て一言、
「あぁ、君が次代の勇者か」
半分以上胴体から分かたれた顔で言った。
「勇者は魔王を殺すのが務めだ。そうだろう?君だってその為にここまでやってきたはずだ」
だから、と続けて、
「僕を殺してくれ」
悲しげな顔で、言う。
確かに魔王を倒すためにやってきた。
でも、彼は、“ヒト”だ!
魔物対峙は出来ても、人殺しは出来ない……!
戸惑っている私に彼が追い討ちをかけるように言ってくる。
「何を躊躇する必要がある。僕が魔王なのには変わりないだろう?……この首を切り離したら、恐らく体は一目散に君に襲い掛かるぞ」
「何だと……?」
「今はまだ脳が繋がっていて僕の思う通りに動くが、それを離したら体は“ヤツ等”の制御下に置かれる。僕の意識が戻ってしまうのはきっと想定外だったから取り繕う為にも形振り構わず君を殺すぞ」
“ヤツ等”?
さっきから……一体何を言っているんだ?!
「だ、だったらその手を首からどけたらどうなんだ!繋がっている内は貴方の体のままなんだろう?!」
そう言うと彼は苦く笑った。
「一番良いのは、君がすぐに僕を殺してくれる事。だけどもう“見て”しまったから無理だろう?」
「! そ、それは……」
「顔を無くせば躊躇無く出来るはずだ。――それに、この体から一刻も早く離れたい」
ぐちゅ ぷつ ぷつ ずりっ
黒く澱んだ肌の向こうにすっぱりと切断された骨が見えた。
「あぁ、これかい? 随分前に、斬られたんだよ」
ぷつ ぷつ
「死神に――ね」
ぶつっ ごろん
首が落ちた。
彼の言った通り、体はすぐに襲ってきた。途中、投げ捨てていた杖を拾って先端をこちらへ向けて、走ってくる。
魔法を使わないのは呪文を紡ぎ出す口が無いからか。
明らかに先ほどまでの魔王とは劣るその肉塊を、私は両断する。 血の出ない塊は、2つに分かれて地に転がった。
そして私はもう一つの塊の方へと歩み寄る。
「……困ったね。まだ、意識があるんだ」
顔だけの彼は困ったように笑っていた。
「なんとなくそう思った。下があれだけ普通に動くんだから……さぁ、それで貴方はどうするんだ?体は死んでしまったぞ」
半ば呆れながらしゃがみこんで頭だけの彼と会話する。それは酷く奇妙な光景だった。
「まぁ、心配は要らないと思う。じきにこちらも死ぬだろうから。――だからその前に、伝えておきたい事がある」
真剣な表情、赤い瞳が一度閉じて、開いた。
「国に帰ったら、片っ端から歴史の本を調べてくれ。
巧妙に隠されてはいるだろうが、きっとどこかにあるはずだ」
「ちょっと待ってくれ、何の事だ?」
しかし彼はもうこちらの声など聞こえていないように続ける。
「それから一緒に戦ってくれた仲間には早々に別れを告げるんだ。巻き込みたくないのなら」
瞳が徐々に閉じられていく。今度はもう開かないような気がした。
「そして10日後に気をつけ――――――」
沈黙が広がり、瞳はもう二度と開かれなかった。
そして勇者も生まれました。
勇者は魔王を倒しました。
それでめでたしめでたし――――になったのでしょうか?
そう、くぐもった声が聞こえてきた。
黒いマントに覆い隠された顔の辺りからだった。
「なん……だって?」
チャキ、と剣を構えた。その言葉がよくわからなかったからだ。
「殺せ、と言っているのだ」
やはりくぐもった声。
両手を広げてもう一度同じ言葉を繰り返した。
冗談ではない。
「何を言っているのだ、魔王!!何を考えている!!」
再び剣を構えて間合いを十分に取った。こんな言葉に惑わされるわけにはいかないのだ。
だが魔王は最早戦闘の意思など無いかのように持っていた杖を放り投げる。
そして顔までを覆っていたマントを剥ぎ取った。
現れたのは見目麗しい青年だった。
年の頃は私と同じか、少し上か。
ブロンドに赤い瞳。鎧をつけたその姿はまるでどこかの騎士のようで。
しかし普通と違うのは首に入った線。
無理に縫い合わされたような痛々しいジグザグ模様。壊死しているかのように黒く変色している。
その傷に魔王が触れて言った。
「全てを思い出した」
マント越しではない声はよく通り、どこか悲しげな音色で響いた。
「僕がどうしてこんな所に居るのかも、どうしてこんな事をしているのかも、そしてこの首の傷の理由も」
ぐちゅ
傷に沿って無理やり指を入れていく。プツプツという音と共に縫いとめられていた糸が切れ、首は離れていった。
「なっ、何をしているんだ?!」
気味の悪い光景と、それに似合わない優しげな表情。
そして何より、黒マントの下が自分達と変わらない“ヒト”だったという事に対しての動揺が私を包んでいた。
魔物をいくら切っても、魔王と対峙しても震えなかった腕が僅かに揺れた。
“彼”はそんな私を見て一言、
「あぁ、君が次代の勇者か」
半分以上胴体から分かたれた顔で言った。
「勇者は魔王を殺すのが務めだ。そうだろう?君だってその為にここまでやってきたはずだ」
だから、と続けて、
「僕を殺してくれ」
悲しげな顔で、言う。
確かに魔王を倒すためにやってきた。
でも、彼は、“ヒト”だ!
魔物対峙は出来ても、人殺しは出来ない……!
戸惑っている私に彼が追い討ちをかけるように言ってくる。
「何を躊躇する必要がある。僕が魔王なのには変わりないだろう?……この首を切り離したら、恐らく体は一目散に君に襲い掛かるぞ」
「何だと……?」
「今はまだ脳が繋がっていて僕の思う通りに動くが、それを離したら体は“ヤツ等”の制御下に置かれる。僕の意識が戻ってしまうのはきっと想定外だったから取り繕う為にも形振り構わず君を殺すぞ」
“ヤツ等”?
さっきから……一体何を言っているんだ?!
「だ、だったらその手を首からどけたらどうなんだ!繋がっている内は貴方の体のままなんだろう?!」
そう言うと彼は苦く笑った。
「一番良いのは、君がすぐに僕を殺してくれる事。だけどもう“見て”しまったから無理だろう?」
「! そ、それは……」
「顔を無くせば躊躇無く出来るはずだ。――それに、この体から一刻も早く離れたい」
ぐちゅ ぷつ ぷつ ずりっ
黒く澱んだ肌の向こうにすっぱりと切断された骨が見えた。
「あぁ、これかい? 随分前に、斬られたんだよ」
ぷつ ぷつ
「死神に――ね」
ぶつっ ごろん
首が落ちた。
彼の言った通り、体はすぐに襲ってきた。途中、投げ捨てていた杖を拾って先端をこちらへ向けて、走ってくる。
魔法を使わないのは呪文を紡ぎ出す口が無いからか。
明らかに先ほどまでの魔王とは劣るその肉塊を、私は両断する。 血の出ない塊は、2つに分かれて地に転がった。
そして私はもう一つの塊の方へと歩み寄る。
「……困ったね。まだ、意識があるんだ」
顔だけの彼は困ったように笑っていた。
「なんとなくそう思った。下があれだけ普通に動くんだから……さぁ、それで貴方はどうするんだ?体は死んでしまったぞ」
半ば呆れながらしゃがみこんで頭だけの彼と会話する。それは酷く奇妙な光景だった。
「まぁ、心配は要らないと思う。じきにこちらも死ぬだろうから。――だからその前に、伝えておきたい事がある」
真剣な表情、赤い瞳が一度閉じて、開いた。
「国に帰ったら、片っ端から歴史の本を調べてくれ。
巧妙に隠されてはいるだろうが、きっとどこかにあるはずだ」
「ちょっと待ってくれ、何の事だ?」
しかし彼はもうこちらの声など聞こえていないように続ける。
「それから一緒に戦ってくれた仲間には早々に別れを告げるんだ。巻き込みたくないのなら」
瞳が徐々に閉じられていく。今度はもう開かないような気がした。
「そして10日後に気をつけ――――――」
沈黙が広がり、瞳はもう二度と開かれなかった。