緑の小道。
舗装されていない獣道のような場所をひたすら行く。
太陽の光は木々に遮られるものもあれば、木漏れ日となって降り注ぐものもあった。
ふと脇を見れば可愛らしい小動物がお目見えするような、緑の美しい世界。
手に握った地図を広げて確かめて、この方面であってるよな、と方位磁石で方角を調べながら歩みを進める。
時折磁石を信じて道なき道(獣道なんてものじゃなく、本当に何も無い場所)を進むこともあったが、最終的にはやはり僅かでも切り開かれた道に出てきていたので、間違った方向へは行ってない、と思う。
この森に入って1時間ほど経っただろうか。
少しだけ、広場のような形に開かれた場所へ出た。
真ん中に大きな切り株があって、柔らかな光を受けている。
僕はその切り株に腰を下ろして息を吐いた。
そして背中にしょっていたリュックを下ろして中から水筒とお菓子を取り出す。
お菓子はここに来る前によった街の宿で行きがけに貰ったクッキーだ。
全くのプレーンとココアを含んだ物の二種類。
その素朴で優しい味に思わず笑みが漏れる。
「ありがとう、美味しいです」
聞こえるわけが無いとわかっていても、つい口に出して言った。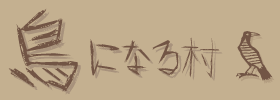 僕の名前はラキ。
僕の名前はラキ。
とある理由があって、この森へとやってきた。
年は……正確なのはもうわからなくなってしまったけれどたぶん16歳くらいかな……。
色素の薄い茶色の髪と青色の瞳。それなりに容姿は整っている方だと思う。
それに右耳に一つ、蒼いピアスをつけている。
サファイアのような美しい蒼のそれは、今回の旅に一番、必要な物だった。
「ん……しょっ、と」
一息ついた所で、もう一度気合を入れて歩き出す。おそらくまだ目的地への半分も進んでいない。
僕は再び道無き道を進むのだった。
あれから2時間も歩いただろうか……景色が変わった。
苔生した岩に挟まれた細い道。 自然に出来たものなのか、人の手によって造られたものなのか。
僕にはその判断は出来なかったが、ふと足元を見て気づく。
――無数の人の、足跡。
「……、……ここ、だね」
思わずごくり、と生唾を飲み込んだ。
この先に……僕の目的地があるはずなんだ。
岩に沿って道は続いていく。 結構入り組んでいるようで、先の方は見通せない造りになっていて、慎重に、でも遅くはならないくらいに、一歩一歩進んでいた。
どれ程歩いただろう。
時間を計る物が手元に無いので正確な時間はわからないが、 相当歩いた気がする。
「……長い、な」
しかし、そう言うが早いか……隙間道は突然途切れ、上へと進む飛び石を残して消えた。
そして現れたのは、明らかに人工的な階段だった。
草を取り除き、土を慣らし、石を敷いて、それは出来ていた。
「……う、わぁ……」
大した高さの物ではないが、思わず見上げてしまう。
僕は急く心を落ち着けながら、一歩一歩上がっていく。
そして、一番上まで上がった時、大きな石が積みあがった、オブジェのような物が視界に入った。
あぁ、これだ。
それに駆け寄って一番上の石に恐る恐る手を近づける。
ひんやりとした感触を手のひらに感じながら、僕は目を瞑った。
……やっと、来ました。
目を瞑ったまま、口を開く。
右耳のピアスは仄かな光を放っていた。
「アーシアル・ウィルダデント」
昔“教えて貰った”言葉を口にして、僕は石の中へと、溶け込んでいった。
◆ ◆ ◆
石に溶け込む感覚が消えてゆく。
目蓋の向こうから明るい光が射してくるのがわかって……、
目を開くと、そこはもう、森じゃなかった。
立ち並ぶ家屋。行きかう人は居ないけれど、明らかに人の居る場所。
僕は首を左右に動かして景色を確認する。そして見覚えのある箇所を見つけて、そちらの方へと走っていった。
やっと、
やっと……!
ハァ、ハァ……、肩で息をしながら、それでも走り続けた。
あの角だ!
あの角を曲がれば開けた場所に出て、
その向こう側に、あの人が!
逸る気持ちを抑えられない。
僕は全速力で走って行って、 角を曲がって、
……え……?
そこ、には――何も、無かった。
いや、あったけれど、それは僕が思い描いたものではなくて、僕の……記憶に残っていたものでは……なく、て。
「な、なんで……?」
へたり、とその場にひざをついた。
脱力感が襲ってくる。
目の前の――廃屋を目にして、ただ、呆然とするしか……無かった。
* * *
何分も何十分もそこに居たような気がする。気がつけば辺りは陽が落ちてオレンジ色に染まっていた。
それに気がついたからどうというわけではない。
しかし、辺りを見渡した事で、近くに人が居るのにも気づいた。
そしてその人は、未だに脱力感を拭えないでいた僕に話しかけてきた。
「どうしたんさね、お前さん」
もうご高齢であろうその人は少し驚いたような表情でそう言った。
僕は率直に訊いた。
「ここの……ここに、住んでいた人は――どうされたんですか?」
僕のその問いにご老人はもっと驚いた顔をして、
「あァ……その人なら鳥になったよ」
ポツリと一言、そう言った。
……。
……。
……???
意味がわからない。
その僕の気持ちは言葉になってすぐに口から出てきた。
「鳥に……なった?」
ご老人は深く頷くと、その手に持っていた杖に寄りかかって、話を始めた。
「一年程前の事になるがの……。
突然倒れてな、医者とか色んな呪い師とかが見たんだけども、原因はわからず意識も戻らんかったんじゃよ。
どうにもあの人にゃあ家族なんちゅーモンはおらんかったようじゃし、そう親しい人もそんなにおらんかったようでのう。ワシはほれ、ご近所さんだったからの、よく見舞いに行ってたんじゃ」
そこで一息ついて、目を瞑った。
「んでも2週間くらい経った頃かのォ、今度は突然居なくなっちまって……探したけんども、見つからんかっての。ワシたちゃぁ、『きっとようなったんだ』、つって探すのやめようとした矢先に――見つけてしまったんよ」
そこまで話した時、ご老人はどこか寂しそうな顔から、突然――嬉しそうな表情を作った。
「……何を見つけたんです……?」
空を仰いでご老人は言った。
「羽さね。 鳥の羽さァ」
「鳥の羽……ですか?」
「そうさね」
淀みなく答えるその口調にからかいなどは一切含まれていない。
だからこそ、奇妙だった。
するとそんな僕の考えがわかったのか、付け足すようにこう言った。
「この村は昔から原因不明の病にかかった人間は鳥になっちょるのよ。
皆医者やら呪い師やらが諦める類のモノにかかって、そんでしばらくしたら消えちまう。
ただ1つ、寝ていた場所に鳥の羽を残しての」
ふぅ、と息を吐く。
そして嬉しそうに顔を綻ばせた。
「鳥になるっちゅー事は神様に近づけるっちゅー事なんじゃ。
皆ヒトじゃった時は空を飛べんじゃろう?でも鳥になる事で空高く舞い上がれる、お天と様に近づけるんじゃよ。
だから村人は皆、鳥に憧れて崇めとる。……まぁ、食べん事も無いんじゃけど」
ワシもいつかは鳥になりたいもんさな……、ご老人はそう、呟いた。
「ところでお前さん、見かけん顔じゃが他所から来なさったんかね?」
突然の質問に少しうろたえつつもコクリ、と頷き返す。
「はい、先ほど来たばかりです」
「そうかい……いや、しかし、よく来れたもんじゃの?ホレ、この村はちぃとばかし特殊じゃろう? 普通全くの余所者は入ってこれんようになっとるんじゃが、一体どういう事なんかの?」
ご老人の疑問は最もだった。
この村は、普通ならヒトの目には映らない場所にあるのだから。
最寄の街から森へ入って3時間、それから岩に挟まれた道を30分程、階段を上がって石のオブジェへ。
これがこの村へ来た時のルート。
本来なら石のオブジェへと来ても、それはただの“オブジェ”でしか無い。
しかしある物を使えば、それは村への入り口となるのだ。
「えぇ、噂に聞いていました。
この村は閉ざされた村なんですよね」
そう、裏を返せば“ある物”を使わなければ入れない場所。
ここは――高度な魔法によって隠された村なのだ。
「このピアスと言葉が導いてくれました。僕、以前ここに来たことがあって、その時に教えて貰ったんです」
右耳のピアスを見せながらそう言った。
ご老人は「なるほどの」としきりに頷いていた。
いつの間にやら陽は完全に落ち、辺りは暗くなっていた。
今日はとりあえず宿に泊まろうと思っていたので場所を教えて貰う。
「広場があるじゃろ、わかるかの? そこに風見鶏が入り口の柱にある建物がある。それが宿じゃよ。……いや、身内びいきになってしまうがアレはワシの息子夫婦での、なかなか良い場所なんじゃよ」
ご老人は照れくさそうに笑った。
「ありがとうございます。じゃあ、そこへ行って泊まることにしますね」
――何だかお引止めしてしまってすみません。
――いや、なに、いいんじゃよ。
そんな会話をしながら広場まで一緒に戻った。
そして道を分かれる時、ご老人は僕を呼び止めて、言った。
「お前さん、今日はゆっくりとお休み。それでな、朝起きたら最初にまず村長の家へと行きなさい。
ホレ、ここからも見えるじゃろう……あの高台にある大きな館じゃ。
あの方は村人にはそれはもう親切にしてくださるのじゃが、余所者にはとても厳しくなさる。
先にこちらから出向いて、全くの余所者じゃない事をきちんと説明せねばの」
ご老人にはピアスを見せた時に一緒に話していた。
僕がこの村に浅からぬ縁があるという事。
あのピアスをくれたのは――さっきの、廃屋の主だったという事。
「はい、わかりました。
どうも色々とありがとうございます。え、ええと……」
僕が言い淀むとご老人は「あぁ、」と笑う。
「そういえば自己紹介がまだじゃったのう。ワシはアルバフという者じゃ。
アルバフ=ウィザナード。アルさんで良いよ」
ご老人――アルさんは朗らかに笑う。
「僕はラキです。ラキ=フラッパーズと呼ばれています。……最も、“フラッパーズ”は後付けなんですけども」
「ほう? 名前が後付けとは珍しいの?」
少し首を傾げたアルさんに僕は付け足す。
「えぇ、僕は嫌なんですけどね。もう開き直りというか。
小さい頃に竜巻に巻き込まれて“飛ばされて”、家族を失ったので親戚やら施設やらを“飛び回るように”たらい回しにされました。その生い立ちを知ったバカなガキ――あ、失礼、子供が言ったんです。
“flap away - 羽ばたいて飛び去る”……と。
大方遊びで読んだ辞書にでも書いてあったんでしょうが、それを周りの連中もいたく気に入ってしまいまして。そして本当にすぐにその施設から出る予定だった僕にはぴったりで。
それ以来、“flapers”と、名乗ってます」
「ほう……なるほどの……しかし、名前まで何か村と縁があるようじゃ」
ほっほっほとアルさんの笑い声が暗くなった空に響いた。
宿に入ると、すぐに人が居た。
「あ……、お客様、ですか?」
年の頃のなら僕と同じか、もしくは少し下か。 赤茶色の髪をした女の子だった。
「あぁ、泊まれるのかな?」
どうやらここの宿屋は酒場も一緒にしているようで、食事スペースには村人だろうか……結構な人が集まっていた。
「はい!勿論です」
女の子はそう答えるとカウンターの方へと案内してくれた。
「お母さん、お客様っ」
カウンターには女将さんが居て、にこやかな顔で迎えてくれる。
「いらっしゃいませ。お泊りで……お一人様ですね?」
「はい」
「ええと、それでは一泊が1000G、食事など別料金で、宜しければこちらや他で食べて頂くことも出来ます」
酒場の方を紹介しながら女将さんは言う。
まぁ、素泊まり値段だったら相応……いや、安いと思う。
料金は後払い、つまり泊まった分だけ1日の終わりに支払うようになっているらしい。
「では、お部屋に案内しますね」
階段の方へと促されて、2階へと上がっていった。
「えっと……その、ちょっと前に一人用の部屋が汚れてしまって、まだお客様をお泊め出来るような状態じゃないんです。 ですから二人部屋になるんですが……良いですか?あ!勿論、料金は一人部屋の方で計算しますので!」
階段〜廊下、と行く間にそんな事を言われた。
僕は別に問題ないのでコクリ、と頷く。
「大丈夫です。というか少しお得ですね、それだと」
そう付け加えると女の子は笑って「そうかもです」と言った。
キィィ……
ドアを開く音が響く。
部屋の中にはベッドが2つに小さな机が1つ。至ってシンプルな造りだった。
「お部屋はこちらで良いでしょうか?北側のお部屋もありますけど……」
「ううん、ここでいいよ」
窓際へ寄ってみると、広場が見渡せるなかなか良い場所だった。
「じゃあ、これ鍵です。」
チャリ……、手のひらに鍵を受け取って握り締める。 無くさないように気をつけないと。
「あ、そういえば……」
部屋から出て行こうとしていた女の子がくるりと振り返った。
「私、キアラって言います。よろしくお願いしますね」
「僕はラキ。よろしくね、キアラさん」
そう返すと彼女はさっと頬を赤く染めた。
「?」
「あっ、いえ!その……あんまり“さん”付けされる事がないのでちょっと恥ずかしくて。
“キアラ”って呼んでくれると嬉しいです」
……?ふーん、そういうモノなのかなぁ……。 僕としちゃあ呼び捨ての方が恥ずかしい気もするんだけど。
「じゃあ、キアラ。僕の事も“ラキ”でいいよ。
――改めて、よろしくね」
「はい!」
明日の用意を整えてベッドに入る。
何だか今日は疲れてしまった……。
ここまで歩いて来るのも大変だったし、何より。
――あの人が、居ないなんて。
精神的にダメージを受けたというのか……空虚感に溢れたというのか。
ただひたすら、いつかこの地へやってきてお礼がしたかった。
初めて会った時、随分若いような印象だったからそんなに早くに亡くなるなんて思ってなかった。
だって……あれからまだ、10年しか、経ってない。
寝返りをうって窓が見える体制にする。
空は暗くて何も見えない。
――鳥に、なる。
一体それは、どういう事なんだろう……?
僕はそんな事を考えながら、少しずつ眠りへとおちていった。
舗装されていない獣道のような場所をひたすら行く。
太陽の光は木々に遮られるものもあれば、木漏れ日となって降り注ぐものもあった。
ふと脇を見れば可愛らしい小動物がお目見えするような、緑の美しい世界。
手に握った地図を広げて確かめて、この方面であってるよな、と方位磁石で方角を調べながら歩みを進める。
時折磁石を信じて道なき道(獣道なんてものじゃなく、本当に何も無い場所)を進むこともあったが、最終的にはやはり僅かでも切り開かれた道に出てきていたので、間違った方向へは行ってない、と思う。
この森に入って1時間ほど経っただろうか。
少しだけ、広場のような形に開かれた場所へ出た。
真ん中に大きな切り株があって、柔らかな光を受けている。
僕はその切り株に腰を下ろして息を吐いた。
そして背中にしょっていたリュックを下ろして中から水筒とお菓子を取り出す。
お菓子はここに来る前によった街の宿で行きがけに貰ったクッキーだ。
全くのプレーンとココアを含んだ物の二種類。
その素朴で優しい味に思わず笑みが漏れる。
「ありがとう、美味しいです」
聞こえるわけが無いとわかっていても、つい口に出して言った。
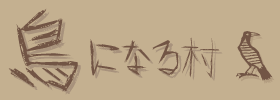
とある理由があって、この森へとやってきた。
年は……正確なのはもうわからなくなってしまったけれどたぶん16歳くらいかな……。
色素の薄い茶色の髪と青色の瞳。それなりに容姿は整っている方だと思う。
それに右耳に一つ、蒼いピアスをつけている。
サファイアのような美しい蒼のそれは、今回の旅に一番、必要な物だった。
「ん……しょっ、と」
一息ついた所で、もう一度気合を入れて歩き出す。おそらくまだ目的地への半分も進んでいない。
僕は再び道無き道を進むのだった。
あれから2時間も歩いただろうか……景色が変わった。
苔生した岩に挟まれた細い道。 自然に出来たものなのか、人の手によって造られたものなのか。
僕にはその判断は出来なかったが、ふと足元を見て気づく。
――無数の人の、足跡。
「……、……ここ、だね」
思わずごくり、と生唾を飲み込んだ。
この先に……僕の目的地があるはずなんだ。
岩に沿って道は続いていく。 結構入り組んでいるようで、先の方は見通せない造りになっていて、慎重に、でも遅くはならないくらいに、一歩一歩進んでいた。
どれ程歩いただろう。
時間を計る物が手元に無いので正確な時間はわからないが、 相当歩いた気がする。
「……長い、な」
しかし、そう言うが早いか……隙間道は突然途切れ、上へと進む飛び石を残して消えた。
そして現れたのは、明らかに人工的な階段だった。
草を取り除き、土を慣らし、石を敷いて、それは出来ていた。
「……う、わぁ……」
大した高さの物ではないが、思わず見上げてしまう。
僕は急く心を落ち着けながら、一歩一歩上がっていく。
そして、一番上まで上がった時、大きな石が積みあがった、オブジェのような物が視界に入った。
あぁ、これだ。
それに駆け寄って一番上の石に恐る恐る手を近づける。
ひんやりとした感触を手のひらに感じながら、僕は目を瞑った。
……やっと、来ました。
目を瞑ったまま、口を開く。
右耳のピアスは仄かな光を放っていた。
「アーシアル・ウィルダデント」
昔“教えて貰った”言葉を口にして、僕は石の中へと、溶け込んでいった。
◆ ◆ ◆
石に溶け込む感覚が消えてゆく。
目蓋の向こうから明るい光が射してくるのがわかって……、
目を開くと、そこはもう、森じゃなかった。
立ち並ぶ家屋。行きかう人は居ないけれど、明らかに人の居る場所。
僕は首を左右に動かして景色を確認する。そして見覚えのある箇所を見つけて、そちらの方へと走っていった。
やっと、
やっと……!
ハァ、ハァ……、肩で息をしながら、それでも走り続けた。
あの角だ!
あの角を曲がれば開けた場所に出て、
その向こう側に、あの人が!
逸る気持ちを抑えられない。
僕は全速力で走って行って、 角を曲がって、
……え……?
そこ、には――何も、無かった。
いや、あったけれど、それは僕が思い描いたものではなくて、僕の……記憶に残っていたものでは……なく、て。
「な、なんで……?」
へたり、とその場にひざをついた。
脱力感が襲ってくる。
目の前の――廃屋を目にして、ただ、呆然とするしか……無かった。
* * *
何分も何十分もそこに居たような気がする。気がつけば辺りは陽が落ちてオレンジ色に染まっていた。
それに気がついたからどうというわけではない。
しかし、辺りを見渡した事で、近くに人が居るのにも気づいた。
そしてその人は、未だに脱力感を拭えないでいた僕に話しかけてきた。
「どうしたんさね、お前さん」
もうご高齢であろうその人は少し驚いたような表情でそう言った。
僕は率直に訊いた。
「ここの……ここに、住んでいた人は――どうされたんですか?」
僕のその問いにご老人はもっと驚いた顔をして、
「あァ……その人なら鳥になったよ」
ポツリと一言、そう言った。
……。
……。
……???
意味がわからない。
その僕の気持ちは言葉になってすぐに口から出てきた。
「鳥に……なった?」
ご老人は深く頷くと、その手に持っていた杖に寄りかかって、話を始めた。
「一年程前の事になるがの……。
突然倒れてな、医者とか色んな呪い師とかが見たんだけども、原因はわからず意識も戻らんかったんじゃよ。
どうにもあの人にゃあ家族なんちゅーモンはおらんかったようじゃし、そう親しい人もそんなにおらんかったようでのう。ワシはほれ、ご近所さんだったからの、よく見舞いに行ってたんじゃ」
そこで一息ついて、目を瞑った。
「んでも2週間くらい経った頃かのォ、今度は突然居なくなっちまって……探したけんども、見つからんかっての。ワシたちゃぁ、『きっとようなったんだ』、つって探すのやめようとした矢先に――見つけてしまったんよ」
そこまで話した時、ご老人はどこか寂しそうな顔から、突然――嬉しそうな表情を作った。
「……何を見つけたんです……?」
空を仰いでご老人は言った。
「羽さね。 鳥の羽さァ」
「鳥の羽……ですか?」
「そうさね」
淀みなく答えるその口調にからかいなどは一切含まれていない。
だからこそ、奇妙だった。
するとそんな僕の考えがわかったのか、付け足すようにこう言った。
「この村は昔から原因不明の病にかかった人間は鳥になっちょるのよ。
皆医者やら呪い師やらが諦める類のモノにかかって、そんでしばらくしたら消えちまう。
ただ1つ、寝ていた場所に鳥の羽を残しての」
ふぅ、と息を吐く。
そして嬉しそうに顔を綻ばせた。
「鳥になるっちゅー事は神様に近づけるっちゅー事なんじゃ。
皆ヒトじゃった時は空を飛べんじゃろう?でも鳥になる事で空高く舞い上がれる、お天と様に近づけるんじゃよ。
だから村人は皆、鳥に憧れて崇めとる。……まぁ、食べん事も無いんじゃけど」
ワシもいつかは鳥になりたいもんさな……、ご老人はそう、呟いた。
「ところでお前さん、見かけん顔じゃが他所から来なさったんかね?」
突然の質問に少しうろたえつつもコクリ、と頷き返す。
「はい、先ほど来たばかりです」
「そうかい……いや、しかし、よく来れたもんじゃの?ホレ、この村はちぃとばかし特殊じゃろう? 普通全くの余所者は入ってこれんようになっとるんじゃが、一体どういう事なんかの?」
ご老人の疑問は最もだった。
この村は、普通ならヒトの目には映らない場所にあるのだから。
最寄の街から森へ入って3時間、それから岩に挟まれた道を30分程、階段を上がって石のオブジェへ。
これがこの村へ来た時のルート。
本来なら石のオブジェへと来ても、それはただの“オブジェ”でしか無い。
しかしある物を使えば、それは村への入り口となるのだ。
「えぇ、噂に聞いていました。
この村は閉ざされた村なんですよね」
そう、裏を返せば“ある物”を使わなければ入れない場所。
ここは――高度な魔法によって隠された村なのだ。
「このピアスと言葉が導いてくれました。僕、以前ここに来たことがあって、その時に教えて貰ったんです」
右耳のピアスを見せながらそう言った。
ご老人は「なるほどの」としきりに頷いていた。
いつの間にやら陽は完全に落ち、辺りは暗くなっていた。
今日はとりあえず宿に泊まろうと思っていたので場所を教えて貰う。
「広場があるじゃろ、わかるかの? そこに風見鶏が入り口の柱にある建物がある。それが宿じゃよ。……いや、身内びいきになってしまうがアレはワシの息子夫婦での、なかなか良い場所なんじゃよ」
ご老人は照れくさそうに笑った。
「ありがとうございます。じゃあ、そこへ行って泊まることにしますね」
――何だかお引止めしてしまってすみません。
――いや、なに、いいんじゃよ。
そんな会話をしながら広場まで一緒に戻った。
そして道を分かれる時、ご老人は僕を呼び止めて、言った。
「お前さん、今日はゆっくりとお休み。それでな、朝起きたら最初にまず村長の家へと行きなさい。
ホレ、ここからも見えるじゃろう……あの高台にある大きな館じゃ。
あの方は村人にはそれはもう親切にしてくださるのじゃが、余所者にはとても厳しくなさる。
先にこちらから出向いて、全くの余所者じゃない事をきちんと説明せねばの」
ご老人にはピアスを見せた時に一緒に話していた。
僕がこの村に浅からぬ縁があるという事。
あのピアスをくれたのは――さっきの、廃屋の主だったという事。
「はい、わかりました。
どうも色々とありがとうございます。え、ええと……」
僕が言い淀むとご老人は「あぁ、」と笑う。
「そういえば自己紹介がまだじゃったのう。ワシはアルバフという者じゃ。
アルバフ=ウィザナード。アルさんで良いよ」
ご老人――アルさんは朗らかに笑う。
「僕はラキです。ラキ=フラッパーズと呼ばれています。……最も、“フラッパーズ”は後付けなんですけども」
「ほう? 名前が後付けとは珍しいの?」
少し首を傾げたアルさんに僕は付け足す。
「えぇ、僕は嫌なんですけどね。もう開き直りというか。
小さい頃に竜巻に巻き込まれて“飛ばされて”、家族を失ったので親戚やら施設やらを“飛び回るように”たらい回しにされました。その生い立ちを知ったバカなガキ――あ、失礼、子供が言ったんです。
“flap away - 羽ばたいて飛び去る”……と。
大方遊びで読んだ辞書にでも書いてあったんでしょうが、それを周りの連中もいたく気に入ってしまいまして。そして本当にすぐにその施設から出る予定だった僕にはぴったりで。
それ以来、“flapers”と、名乗ってます」
「ほう……なるほどの……しかし、名前まで何か村と縁があるようじゃ」
ほっほっほとアルさんの笑い声が暗くなった空に響いた。
宿に入ると、すぐに人が居た。
「あ……、お客様、ですか?」
年の頃のなら僕と同じか、もしくは少し下か。 赤茶色の髪をした女の子だった。
「あぁ、泊まれるのかな?」
どうやらここの宿屋は酒場も一緒にしているようで、食事スペースには村人だろうか……結構な人が集まっていた。
「はい!勿論です」
女の子はそう答えるとカウンターの方へと案内してくれた。
「お母さん、お客様っ」
カウンターには女将さんが居て、にこやかな顔で迎えてくれる。
「いらっしゃいませ。お泊りで……お一人様ですね?」
「はい」
「ええと、それでは一泊が1000G、食事など別料金で、宜しければこちらや他で食べて頂くことも出来ます」
酒場の方を紹介しながら女将さんは言う。
まぁ、素泊まり値段だったら相応……いや、安いと思う。
料金は後払い、つまり泊まった分だけ1日の終わりに支払うようになっているらしい。
「では、お部屋に案内しますね」
階段の方へと促されて、2階へと上がっていった。
「えっと……その、ちょっと前に一人用の部屋が汚れてしまって、まだお客様をお泊め出来るような状態じゃないんです。 ですから二人部屋になるんですが……良いですか?あ!勿論、料金は一人部屋の方で計算しますので!」
階段〜廊下、と行く間にそんな事を言われた。
僕は別に問題ないのでコクリ、と頷く。
「大丈夫です。というか少しお得ですね、それだと」
そう付け加えると女の子は笑って「そうかもです」と言った。
キィィ……
ドアを開く音が響く。
部屋の中にはベッドが2つに小さな机が1つ。至ってシンプルな造りだった。
「お部屋はこちらで良いでしょうか?北側のお部屋もありますけど……」
「ううん、ここでいいよ」
窓際へ寄ってみると、広場が見渡せるなかなか良い場所だった。
「じゃあ、これ鍵です。」
チャリ……、手のひらに鍵を受け取って握り締める。 無くさないように気をつけないと。
「あ、そういえば……」
部屋から出て行こうとしていた女の子がくるりと振り返った。
「私、キアラって言います。よろしくお願いしますね」
「僕はラキ。よろしくね、キアラさん」
そう返すと彼女はさっと頬を赤く染めた。
「?」
「あっ、いえ!その……あんまり“さん”付けされる事がないのでちょっと恥ずかしくて。
“キアラ”って呼んでくれると嬉しいです」
……?ふーん、そういうモノなのかなぁ……。 僕としちゃあ呼び捨ての方が恥ずかしい気もするんだけど。
「じゃあ、キアラ。僕の事も“ラキ”でいいよ。
――改めて、よろしくね」
「はい!」
明日の用意を整えてベッドに入る。
何だか今日は疲れてしまった……。
ここまで歩いて来るのも大変だったし、何より。
――あの人が、居ないなんて。
精神的にダメージを受けたというのか……空虚感に溢れたというのか。
ただひたすら、いつかこの地へやってきてお礼がしたかった。
初めて会った時、随分若いような印象だったからそんなに早くに亡くなるなんて思ってなかった。
だって……あれからまだ、10年しか、経ってない。
寝返りをうって窓が見える体制にする。
空は暗くて何も見えない。
――鳥に、なる。
一体それは、どういう事なんだろう……?
僕はそんな事を考えながら、少しずつ眠りへとおちていった。
TOP | NEXT