――拝啓 お元気ですか?
私は相変わらず文字と格闘する毎日を送っています。上手く繋がる時はいいのだけれど、なかなか繋がってくれずいつも完敗ですけどね。……貴方の話を聞いていた頃が懐かしいです。
あの時はその話を聞くだけでウズウズして、ペンを走らせるのが大変なくらいすぐに文章が出てきたのに。
メイリンは元気でしょうか?私が最後に見た時は10歳の誕生日を迎えた頃でしたよね。
――あれから3年。まだ早いかもしれませんが、メイリンの事だもの。もう立派な魔法使いになっていてもおかしくないですね。私にはよくわからない事ばかりでしたが、素質だけはあると思いましたから。
お師匠様も元気ですか?……相変わらずピーマン残してるのかしら?まぁ、あのピーマン嫌いをなくしたら彼が彼でなくなってしまうような気もするけどね。
あと少ししたら、お休みがいっぱい入るみたいです。
前と比べるとちょっと遠くなったけど、今回の休みは本当に長いので、久しぶりにそちらへお邪魔させて頂こうと思います。……いいですよね?
たぶん4月の中ごろにはそちらへ着けると思います。溜まっている原稿があるから荷物が重くなりそうなの。何となくそっちでやった方が捗るような気がしてね。
正確な日時が決まったらまた連絡しますので。……普通の格好で迎えに来てください。くれぐれも黒ずくめなんかで来ないでくださいね。前にあの格好で来て、警備隊に連れて行かれそうになったこと、覚えていますよね?あの時は本当に焦ったんですから。
それでは、次に会える日を楽しみにしています。
体に気をつけて、お仕事頑張ってくださいね。
――エステア=リーマイン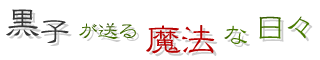
- 序章 「出会いは微妙でしたけど」 -
新しいことを始めると、失敗することもあるが意外な発見を得られることもある。
これは私の自論。でも、たぶん本当の事。
* * *
いつもは通ったりしない道を行くと、そこには家が建っていた。
大きくも、小さくもないものでかなり庶民的な造りのようだ。
薬草を探しに森へ入ったはいいが、最初の角をいつもと反対に曲がったのがいけなかったのだろうか?
実は……迷ってしまっていたようなのだ。
そして、半ばさ迷いながら歩いていた時、この家を見つけた。
屋根から飛び出ている煙突からは白い煙があがっている。という事は人が居る、という事なのだろう。
もう日も暮れる。
私は意を決して、その家の方へと向かっていった。
――ついでに言うと、探しに行った薬草はまだ手に入れていない。
家の近くまで行くと、美味しそうなシチュー(と思われる)の匂いが漂ってきた。匂いで判別するのは苦手……というか、ほとんど出来ないのだが何故かこのシチューはわかった。
これは私の好きなホワイトシチューの匂いだ。
少し意地汚いかもしれないが、私は鼻をひくひくとさせながらその匂いの元へと近づいていった。
あと3メートル……2メートル……1メートル――、少しずつ玄関のドアが近くなってくる。そして、あと少しでそのドアノブに手が届きそうになった時、その声が聞こえたのだ。
「あれ? お客さんですか?」
その声は……何処から聞こえたのか、わからなかった。
声がした瞬間、私は咄嗟に周りを見た。けれど……人影はない。
「お客さんのようですね……、いやはやご主人様の刺客かと思っちゃいましたよ」
姿は見えないのに声だけが聞こえる。その声は、すごく嬉しそうに笑っていた。
「いやぁ、うちのご主人様って結構刺客が多くって、全く世の中腐ってますよねぇ」
はっはっは、と遠くとも近くともとれない場所から笑い声が聞こえてくる。
辺りは一気に暗くなり、私の近くにも暗闇が忍びよ――……ん?
見間違いかもしれないが、私のすぐ傍まで来ていた暗闇が動いたような気がしたのだ。小さく、なのだが。それに……だんだんと近づいてくるのはわかるのだが、かなり早いペースだ。
私は思わず、身構えた。そして口を開ける。
「だ、誰なんですか!?」
するとその暗闇ははた、と立ち止まり――笑った。
「……そういえば、まだ紹介してませんでしたね〜」
そう言って光の下に出てきた人(男か女かは判別が出来なかった)は……やはり黒かった。
全身が黒ずくめ。――とか言うよりもこれは……。
私がその姿を見て驚いているのをまるっきり無視して、その人は手を差し出した。
「あ、どうも。黒子って言います」
「く……ろこ……?」
にこやかに差し出された手と、笑っているのだろう顔がある部分とを見比べた。
そして、(一応)手を握り返す。
「えぇ、黒子。楽しいですよ〜、気づかれないように人の後ろに立ってみたり。こっそりと後を付まわしたり」
……。
「あ、今こいつ変態だ、とか思いましたね?!思ったでしょう!」
――……何でわかったんだろう。心の中で小さく呟いたのは、まさしくソレだった。
「ふん、いいんです。皆この楽しさを知らないだけなんですから!」
ぷんすか、と怒っているのだろうか?顔が見えないので、声で判断するしかない。
彼は(ずっと“その人”と呼ぶのは大変なので仮に“彼”と呼ぶことにした)腕を組みながら何かを考えているようだった。しばらくしてその考え事が終わったのか、私の方をちらりと見て(だと思う)訊いてきた。
「ところで、貴方はどうしてこんなトコに? 辺鄙だし、人はめったに近づかないんですよ?」
そう言う彼に、私は事情を説明した。とどのつまり、薬草を探しに出て道に迷ったのだということを。
「なるほど、確かに普通は皆さんこっちの道には来ませんもんねぇ。あ、もしかして知りません?この家、化け物屋敷って言われてるんですよ」
まぁ、実際に化け物居るんであながち嘘とも言えないんですけどね、と彼はまた笑った。
「ば……けものが居るんですか……?」
思わず後ずさった。そういえば近所の人達がそんな事を話していたような気がする。
「あ、大丈夫ですよ。取って食いやしませんて」
「当たり前ですっ!!」
相変わらず、はっはっはと笑いながら言う彼に、私は声を上げた。
「だいたいっ……あなたは誰なんですか?! こんな所に黒子なんて必要ないでしょうっ?!」
すると彼は驚いて(だと思う)言った。
「あっ、心外ですねー。黒子っていうのは何処に居てもおかしくないと言われているのに」
「そんな事言われてるんですか……?」
「はっはっは、嘘に決まってるじゃありませんか」
――……こ、こいつ……!!
私がその言葉に怒ったのを見たのか、それとも元々こういう性格なのか、彼は思い出したように話題を巧妙にすり替えた。
「さて、もうすぐ夕食の時間ですね。あと少しでもシチューを放って置いたら大惨事になりそうです」
心配をしているような台詞。でも口調だけで判断すると全然、これっぽっちも心配しているように思えない。
「いやはや、別にあの家が火事になろうとどうでもいいんですがね。やっぱりシチューだけは守り抜きたいじゃないですか。僕、シチュー作るの上手いんですよ〜」
……“家<シチュー”の方程式を作る彼。――……一体、何なんだろう?
「どうです?もう遅いですし、良かったら一緒に食べます?」
そう言って彼は、親指を立てた手で後ろの家を指差した。……とは言っても、「黒子」が勝手にそんな事を決めてもいいのだろうか?どう思っても、「黒子」は家の主人じゃないような気がする。
「え、でも……」
言い淀む私に、彼はきょとんとして……でもすぐに笑って言った。
「あぁ、大丈夫ですよ。あの家の金握ってんのは僕ですから。ある意味最高権力者ですしね」
そうでなければあの人達、今頃飢え死にしてますってば、と手をはたはた振りながら続けた。
私はそんな彼にかなりな疑問を覚えながらも、軽く頷く。
「……そ、それじゃ……ご一緒させてください……」
「よし。 それじゃ、どうぞ。 ちっこい外見ですけど、中身は無意味に広いんですよー」
周囲もだんだんと暗くなってきて、その闇に溶け込むように存在する彼。私は彼の言葉に首を傾げながら、その後に続いた。
――近づくにつれ、シチューの匂いが増していった。
* * *
「馬鹿者! 何度言ったらわかるんだ。
火を出すときは右手を逆時計回りに2回転して印、だっつってるだろーが!!」
「んな説明初めて聞いたし。師匠、いくら年だからって急速にボケんのマジ困るんでやめてくださいー」
黒子に案内されて入った家からは、こんな会話が飛び出してきた。
「あ、あの……」
「はい?」
相変わらずどんな表情かわからない(まぁ、黒子だから仕方がない事なのだけど)彼に、私は恐る恐る話しかけた。
「……こっ、この声はどちら様で?」
大方予想はついているけれど、何となく外れていて欲しいなぁ、なんて思ってみる。
「あ、このクソ煩い馬鹿ダミ声ですか?」
けれども黒子は絶えず嬉しそうな声を出し、私の思っている事、ドンぴしゃな答えを返してくれた。
「“一応”この家のご主人様ですよ。 そしてもう一人はご主人様に弟子入りしている子です」
どっちも腐りきってますけどね〜、とあくまでにこやかに言い放つ。
……って、腐っても“ご主人様”なんじゃ。そう思うけれど、先ほどの彼の言葉『最高権力者』発言から考えるに。“ご主人様”なんて露ほども、いや、もしかすると“僕(しもべ)”くらいに思っているのかもしれない。
「な、なかなか賑やかなご家庭で……っ」
自分でもよくわかる、限りなく引きつった笑みでそう返した。
コンコンコン
「ティカさん、メイリン。 そろそろ食事にしますよー」
彼は罵声が飛びまくっていた部屋のドアとノックし、呼びかけた。そして慣れた手つきで液体入りのバケツを紐で吊るしている。――はい?
+ + +
「あぁ、わかった。 ったく、メイリン、後片付けしとくんだぞ!」
「何言ってんの、師匠ってば。 今日の片付け当番は師匠じゃないですか」
マジにボケなんですかい、とソプラノの声で毒舌は続く。
「何ぃ?! 師匠に向かってその口の聞き方は何だ! こらっ、メイリン待ちなさい!!」
今にも掴みかかろうとする“師匠”に向けて、メイリンはにっこり笑った。
そして、――右手を逆時計回りに2回転、そして印。
ボムッ
「んなあぁぁっっ?!?!」
「あ、ホントに炎だ」
師匠に向けて特大の炎を放ったと言うのに、術が成功した事しか頭に入らないらしい。後ろの方で服に移った炎を消すのに大奮闘してる師匠を他所にメイリンはドアを開けた。
ザッバーーンッッ
「……………………」
ガランッ カランッ ……
ドアを開けると上からざばーっ、その後には空っぽバケツがごろんごろん。
「あっはっは、そんな初歩的なモノに引っかかるなんて。メイリンらしくないですよ?」
どう考えてもコイツが仕掛けた、その罠(?)にメイリンは青筋を立てる。
「くぅーろーこー?!!!!」
可愛らしい顔がかなり怒っているのも気にせずに、黒子は動いた。
――手拍子1回、右手を時計回りに1回、十字を切って、最後に印。
ボボボボッ ボボムッ
「「んなあああぁぁぁぁっっっっ?!?!?!」」
黒子が火を放ったかと思うと、突然部屋が爆発した。……さっきのバケツの中身、油だったらしい。
「あつっ、あつあつあつあつあつつつ?!?!」
「はっ……、早く消化を! 水っ、水の呪文!!師匠ぉっ!!」
「水の呪文、水の呪文……って馬鹿、オレを何だと思ってるんだ!呪文なんかなくたってええぇああっつぅ!!」
+ + +
「……ご、ごめんなさい。やっぱり私帰った方がいいんじゃないかと思ったりなんかしたりするんですけど」
ドアの向こうは炎一色なのに、不思議に熱さは感じなかった。むしろ、寒い。
「え? あ、ダメですよ。今この森を生身の人間が一人で歩くと危険過ぎます」
「……そ、それってどういう――」
聞きたくないような気がかなりしたが、私は訊いてしまった。
彼はくすり、と笑うとドアを閉めながら答える。
「いやぁ、ここらへんってモンスターの巣窟なんですよね。と言っても、ほとんどご主人様が作った“メイリン用”のなんですが。 でもメイリンを襲うだけじゃないですから、ダメなんですよ」
そしてまた、ドアを開けた。
ドアの向こうの火はいつの間にか収まっており、中にはずぶぬれになった人達が居た。
「あれ、お二人とも随分と濡れてらっしゃる。 それじゃご飯の前にお風呂にしますか?」
いけしゃあしゃあと言い放つ彼を見て、私は思わず後ずさる。
……とんでもない所に来てしまったかもしれない、そう思ったからだった。
* * *
結局私はこの家に今晩だけお世話になることにした。……というか、お世話にならなきゃいけない状態に陥ったからなのだけど。もし大丈夫なんだったらすぐにでも逃げ出したい気がする。
「ちょっと黒子、聞いてよ!師匠ってばあたしの事馬鹿って言うんだよ? この天才なあたしを捕まえて、馬鹿!ねぇっ、信じられる?!」
「何言ってやがるっ!大体、オレはお前に才能があるだなんてカケラも思っていない!」
「――んー、まぁ、どうでもいいですけど。少しでも下に物零したらとりあえず一ヶ月ご飯抜きますからね」
こんな会話が、さっきからずっと続いているのだ。
ちなみに食事を始める前に私がここに来た理由と一緒に、紹介もしてもらっていた。
“師匠”と呼ばれている男性――私と同い年くらいかもしれない――はティカさんと言うらしい。珍しい水色の髪が印象的な人だ。 そしてその“お弟子さん”のメイリンちゃん。フルネームは「メイ=リンドネス」と言い、メイリンというのはニックネームだそう。年は今年で9つだと聞いた。
……外見的には二人ともとても良い部類に入る筈なんだけど、さっきからの会話で十二分にわかるこの口の悪さ。しかもその上を行く彼――黒子。
やっぱり、私はとんでもない所に来てしまったのかもしれない。
その匂いに釣られてやってきてしまったホワイトシチューを啜りながら、私はまた考えた。
「ごちそーさまでしたっ!」
パチンッ、と手を合わせてメイリンちゃんが言った。いつもそんな風に、可愛らしい声で可愛らしい事を言えばいいのに、と知り合って間もないのに思ってしまう。
「ごちそーさん。 さて、修行の続きだ。メイリン、来い」
メイリンちゃんのすぐ後に同じように食後の挨拶(?)をして立ち上がるティカさん。その表情は見るからに怒っていて、それに対するメイリンちゃんの顔はとても不機嫌そうだ。
「えーっ、今日の分はもう終わったじゃんか。師匠はちょっとしごき過ぎ!」
「これでもミライザに比べたらマシな方だ!ぐだぐだ言わずにさっさと来い」
そう言ってさっと手を振った。
すると何もない筈なのに、メイリンちゃんの体が浮き上がって、ティカさんの後を追いかけるように部屋から出て行った。勿論、というのか……メイリンちゃんは怒っていたようだけど。
二人が出て行った扉を見つめていると、横から彼が声をかけてきた。
「エステアさん♪ シチュー、どうでした?」
「あ、えぇ。 とても美味しかったです」
彼は黒子特有の被り物を口元が見えるくらいの所まで引き上げて食事をしていた。まぁ、そうしなければ物を食べることが出来ないから仕方がないのかもしれないけど……とことん、怪しい。
「それは良かったです。このシチューは自信作ですからね〜」
おかわりとか入ります?、とテーブルの真ん中に置いてある鍋を指差しながら訊いてくる。
私は首を横に振った。
「もうお腹いっぱいです。シチューもですけど、全部本当に美味しかったですから」
シチューの他に出されたのは、とても柔らかいパンとサラダ。それにフルーツジュースだった。本当にお世辞ではなく、美味しかった。
「そうですか。いやぁ、嬉しいですねぇ。いつもあの二人は人が一生懸命作ってるものに対して何も言ってくれないもんですから。 ――ただの栄養補給としか思ってないんです、あの馬鹿共は」
彼はちょっと悲しそうにして(あくまで、雰囲気だけど)肩を竦めた。
私はそれに笑うことも出来ず、ただ曖昧な返事を返した。
食事を終えた後、私は彼の後片付けを手伝うことにした。「お客様は座っててください」と言われたけれど、私は譲らなかった。というのも、“誰かと一緒に”後片付けをするという事が久しぶりで、嬉しかったからだ。
「すみませんねぇ。 それじゃ、僕が洗いますから、その布巾で拭いて貰えますか?」
「えぇ」
隅にかかっていた布巾をとって、彼の隣に並ぶ。暫くの間は私の元に食器は来ない。洗い終えた食器が来るまで私は彼の手元を見ていた。
外で見たときとほとんど同じような服装だったけど、今は腕まくりをしていて素肌が見えている。やっぱり“彼”は男だったようで、私よりも随分逞しい腕が水をうけていた。
その様子を見ながら、私はふと思いついた事があり、それを口にした。
「……そういえば、貴方の名前は何て言うんです?」
そう、さっきの紹介では彼の事は一切触れられなかったのだ。
「僕の名前、ですか? うーん、そうですねぇ……何でしたかねぇ」
「何でしたかねぇ……って、自分の名前でしょうっ!?」
すっとぼけた答えに、思わず声を大きくしてしまう。すると彼は手を止めてこっちを向いた。
「いやいや、嘘ですって。ちゃんと覚えてますよ……けど、そう簡単には教えられません♪」
えっへん、と何故か勝ち誇ったように言われて一瞬カチンと来る。
「……べっ、別に教えて貰わなくてもいいですけどっ。 何て呼べばいいかわからないから――」
本当に何故かわからないのだけど、一気に頬が熱くなる。私は若干紅くなっているだろう顔を隠すように、彼に背を向けた。彼は、驚いたようだった。
「っ……僕の呼び方、ですか。 ……はは、何だか嬉しいですね。 よし、それじゃ特別に問題です!」
「問題?」
「えぇ、問題です。 僕の名前を当ててみてください。あ、4択ですから成功率は25%ですよ」
私は変な事を言い出した彼の方に向き直った。彼はまた手を動かし始めた。
「その1、ケント。 その2、ライザ。 その3、セシア。 その4、スイカ」
さぁ、どれだと思います?彼は顔だけをこっちに向けてそう言った。
……ケント? ライザ? セシア? スイカ?
一つ一つを反復しながら顔の顔と見比べる。……何となく、その4だけは違うような気がした。何故ならそれを言った時に少しだけ笑ったから。となると、選択肢は3つに絞られる。
私は腕を組んで考えに考えたけど、どれも合っている様で、どれも外れている様で。全くわからなかったので、ふんふん♪と鼻歌を歌いながら洗い物をする彼の服の裾を引っ張った。
「ヒント……ください」
「ふむ、ヒントですか。……アルファベットで書くと、“E”の文字が入りますね」
アルファベットで“E”。と言う事は、ケントかセシア?
再び思考時間に入る。……そして、私はある事を考えた。
「今から私が名前を呼びますから、合ってても違っても返事をしてくださいね?」
そう言ってから、息を吸い込む。
「――ケントさん」
「はい♪」
反応は完璧にふざけたもの。……これではないのかもしれない。
「――ライザさん」
「はいはい」
選択肢には入っていないけれど、一応言ってみる。……うー、でも、これも違うような気がする。
「――セシアさん」
「はい?」
顔は見えないけど、明らかに面白がった声。
「――ス、スイカさん」
「……はいv」
だ、だめだ……余計にわからなくなっちゃった。
仕方が無いので、「もう適当に言うしかない!」と無理やり自分を納得させる。
そして適当に、一つの名前を口に出した。
「その3、セシアさんですよね?」
彼は一瞬手を止めて……、すぐに笑った。
「はっはっは、いやだなぁ。 何でわかったんですか?」
「えっ、本当に合ってるんですか!?」
驚いて言うと、彼は何も言わずに少し肩を竦めた。……その動作を見て、嫌な予感が胸を掠める。
「……もしかして、どの名前を言ってもそう言うつもりだったんじゃないでしょうね?」
「はっはっは、いや〜、わかっちゃいましたか〜♪」
彼は悪びれもせず、そう返してきた。あまりにさらりと言うものだから、私は怒ることも忘れただ呆れていた。けれどもよくよく考えるとやはり腹が立ってくるもので。
「何ですかそれ。 ……もう、いいですよ!勝手にセシアさんって呼びますからっ」
「えぇ、何とでもお呼びください。 エステアさん♪」
自分だけちゃんと名前を呼んでズルイ、と思ってしまうのは仕方のない事だろうか。
私はやっと洗い終わってやってきた皿を受け取ると、ちょっと乱暴に水滴を拭き取った。
「よし、これで終わりです!」
拭き終わった食器を食器棚へ戻し、私は深く頷いた。
「どうもありがとうございました。 おかげで今日はいつもより随分早く終わりましたよ」
後ろでは彼が同じように頷いているところだった。
後片付けも一通り終わり、私は夕食時と同じ席に腰を下ろした。
「本当に助かりましたよ。 エステアさん、いつもやってらっしゃるんですか?」
彼はまだキッチンの方に居て、ちょこちょこと色んな所を拭いているようだった。
「えぇ。 一人暮らしだから、どうしてもしなきゃならないんですよ……」
「一人暮らし?」
呟くように言ったのに、彼には聞こえていたらしい。手を止めて、訊き返してきた。私はその言葉にしばし沈黙した後、ウーンと唸りながら答えた。
「ほら、この森の麓に青い屋根の家があるでしょう? 私、そこで暮らしてるんです」
彼が知っているとは限らないけど、私の家はどこかへ出かけるには必ず通らなければならない道の脇に建っているから、もしかしたらと思ってそう言ってみる。
すると彼はぽん、と手を叩いた。
「あぁ! ってことは、エステアさんはイウラ先生の娘さんですか?」
「父を知ってるんですか?」
家の場所はともかくも、まさか父の名前が出てくるとは思わず。驚いて彼の方を見る。
「勿論ですよ。 いやぁ、僕とした事が、“リーマイン”っていうので気づくべきでしたね……」
そう言いながら、こっちへやってきて、椅子に座った。
「そうですか……あのイウラ先生の娘さん――でも、一人暮らしって……先生はどうされたんですか?」
……。
何も知らないような口調に、一瞬頭が真っ白になる。
「父は……両親は亡くなりました。 一年ほど前ですけど」
かろうじて出した声の後に頭に浮かんだのは、思い出したくも無い光景で。私は思わず両手で顔の脇を抑える。 何とかそのイメージを消そうとするけれど、そうすればするほど、それは鮮明になっていった。
青ざめて戻らない顔色、衰えていく体、それでも微笑う表情。
あんなに早く逝ってしまうなんて、あんなに頑張ってたのに……なんでっ……。
「……テアさん、……エステアさんっっ!!!」
「え……?」
頭を抱えていた腕を彼に掴まれる。
私は顔をあげた。
「――すみません、僕知らなくて……本当にすみません……」
謝ってくる彼に私は首を振る。そして離してくれ、というようにそっと掴まれていた腕を動かした。 けれど彼はそれを離さず、とても悲しそうに言った。
「謝りますから、――泣かないでください……」
私の瞳からは、いつの間にか大粒の涙が零れていた。
* * *
「……大丈夫ですか?」
コトン、と湯気のたつ紅茶が入っているカップを置きながら、そう訊かれた。
「えぇ。 私の方こそすみません、いい加減慣れなきゃいけないのに……」
彼はもう一つのカップを自分の手元に残したまま、向かいの席に座った。
「別に慣れなくてもいいですよ。 ……居なくなるのは、寂しいことですから」
何処か悟ったような口調に少しだけ疑問を覚えたけれど、私は「そうですね」と呟き返すだけにした。
暫くは、お互いが紅茶を飲む音と時計が進む音だけが聞こえていた。
けれどずっとそんな気まずい雰囲気のままでいるわけにもいかない。私は、意を決して、声をかけた。
「あ、あのっ」
「あの……」
全く同時に、彼も声を出した。
「あああっ、いえっ、そちらからどうぞ!!」
「い、いえ――……やっぱり僕からいかせてもらいますね♪」
なんだそりゃ。最初の方はこっちに譲るような事を言おうとしていたんだろうに。
何だかおかしくなって、思わず笑ってしまった。
すると彼も笑って、「笑ってくれましたね。良かった」と嬉しそうな声で言った。
「あの、さっきの話を蒸し返すようで悪いんですが……エステアさんは今、何をやってらっしゃるんです?」
“さっきの”というのは、父さんの事だろう。ということは、今の……仕事の事?
「両親の意思を継いで、薬師をやっています」
そう、母さんは本業じゃなかったけれど、父さんは薬師をしていた。薬師とはとどのつまり、「薬を調合する人」だ。そしてそれを村の人や、町の医者に売っていた。
「と言う事はもしかして、今日森に居たのも……薬草を取りに来ていたんですか?」
「はい、この森は昔から貴重な物が多いですから」
紅茶を飲みながらそう返す。
「でも……、それなら何であんな所に居たんです?」
こっち側は危ないばかりで何も無いんですよ?、と更に付け加えられ、私は押し黙る。
そしてちらり、と視線を彼の方へ向けた。
「……笑い、ません?」
「? はい、笑いませんよ」
私の言葉に首を傾げる彼を見て、言おうかどうか迷う。しかし此処で「やっぱりや〜めた」なんて言っても納得して貰えないような気もする。
私はかなり小さな声で、理由〈わけ〉を話した。
「――いつもと違う道に行ったら、いつもと違う“何か”が見つかるかと思ったんです」
テーブルに肘をつき、顔の前で手を絡める。
「違う“何か”を見つけたら、それが違う世界に招待してくれそうな気がして。
そんな風に考えていたら、いつの間にか違う道を選んでたんです」
我ながらかなり夢を見ている発言だと思う。けれど本当の事だったから、自然と口に出来た。
そして、自分の思ってることがちゃんと言えた、と、ある意味誇らしい気持ちで彼を見ると……
「……ぷっ。 あは、あは、あはははははははっっっっ!!!」
……思いきり、笑われた。
「わ、わ、笑わないって言ったじゃないですかっっ!!!」
「あ、いやっ、すいませんっ。 でもおかしくて……っあはははっ」
ぶちっ
笑わない、と言ったくせにこの爆笑。幾ら温厚な私だって腹が立つ。 頭の奥で何かがキレたような音を聞きながら、私は無意識に立ち上がって彼の方へと歩み寄った。
いきなり立ち上がって、しかも寄ってきたのが怖かったのだろうか。彼は突然笑いを止めると、弁解をするように両手を前に出した。
「え、あ、いや、違うんですよっ」
「なぁーにぃーがぁー、違うんですかっ! セシアさんの馬鹿ぁっ!!」
ぽかぽかぽか、とそれほど強くない力で叩く。
彼はそれを受け止めながら、また、違うんです、と言った。
「エステアさんの事を笑ったんじゃなくて――昔、同じ事を言ってたヤツの事を思い出したんですよ! それでその時の事を思い出して、笑ってたんですっ」
ピタッ
彼が捲くし立てるように言った言葉に、一瞬手を止める。
「……ホントですか?」
「ホントです!」
訝しげな表情でそう訊くと、間髪入れずに答えが返ってきた。
その雰囲気(生憎表情はわからないので)が本当っぽかったので、私は手を下ろして、元の席に戻った。
「それにしても、エステアさんってお話が好きな方なんですねぇ」
「……また笑うつもりでしょう?」
「まさかぁ! それにさっきのは違うって言ったじゃないですか」
「セシアさんの言い方だと、いまいち信用出来ませんっ」
今度は別の意味での笑い(である事を願う)と共に言ってきた言葉に私はツンとして返す。
そんな私に、彼は笑って
「仕方ないですねぇ。 それじゃとっておきの物を見せてあげましょう♪」
と言って立ち上がった。
彼が向かった先はキッチンの冷蔵庫の横にある棚。一冊の本?……を取り出した。
「これ、何だと思います?」
「……さぁ? 家計簿?」
思ったままの事を口に出すと、彼は少しガクッときたようだ。
「なんで僕が家計簿なんてつけなきゃならないんですか……日記ですよ、日記!!」
「日記? セシアさんは日記をつける方なんですか」
それを持って元の席に戻ってきた彼にそう声をかける。
「えぇ、長い人生ですからね。 一応何があったのかは把握しておかないと、って思いまして」
パラパラ、と随分分厚いソレを捲っていく。
私はその様子を見ながら訊いた。
「――それがどう、とっておきの物なんです?」
彼はおもむろにソレを閉じ、私の方へ差し出すとこう言った。
「僕の日記を見て、物語、書いてみませんか?」
* * *
「……はい?」
差し出された、そのままの格好で私は思わず声をあげた。
「いや、だから、お話を書いてみませんか? って言ってるんですけど」
最初の言葉とは少しだけ変えて、言ってくる。
「え、ちょっと待ってください。 ……何でお話、なんですか? っていうか何で私?」
「エステアさん、お話考えるの好きなんですよね。 だから、もし良かったらどうかな〜、って」
まだ混乱する私を他所に、彼は話し始める。
「ちょっと前から考えてたんですよ。僕はこうしてあの馬鹿共を養ってやってるんですが、どうも刺激に欠ける生活なんですよね〜。なので、毎日の終わりに日記を書いても何だかつまらなくて。
でも、ですね。ふと思ったんです、この僕等の日常を誰かが「話」にしてくれないかな、って。 僕は日記ならまだしも、そういう物を書くのが苦手だから……ね、ダメですか?」
ずいっ、と顔を近づけられ……一瞬だけど、その黒い布の向こうに黄色い瞳が見えたような気がした。
私は本当に話を考えるのは好きだったし、彼の話は面白いと思った。そして何より、一瞬布越しに見えた表情を見て、私はすぐに首を縦に振った。
彼はそれを承諾の印と、とって、「良かった」と呟いた。
そして日記を改めて私の方へと差し出して、言った。
「僕の一人称で語られて、エステアさんはそれを僕から聞いた話、という事で書いていくんです。
物語の登場人物はとりあえず4人。 語りべの“僕”に、メイリンとティカさん。そしてエステアさん。他は――時々出てくるイレギュラーな人達、とか」
嬉しそうに話す声に、こっちまで何だか嬉しくなってしまう。
「楽しそうですね」
そう言うと、彼は少しだけ声を抑えてこう返した。
「えぇ、楽しいですよ。 だから……それを残してくれる人をずっと探してたんです」
そして、私の手をとり、呟くように付け足す。
「……やっと、見つけました。きっと、エステアさんが今日違う道を行ったのも運命だったんで――」
バタンッッ
「師匠っ!! 黒子がエステアお姉ちゃんを口説いてるよ! 早くっ、ほらっっ!!!」
「馬鹿、メイリン!こういうのは影からそっと見なくちゃいけないんだぞ! わかったら早くドアを閉めなさい!」
パタン
……。
…………。
え、えぇ……っと……。
未だに握られているその手を少し動かして彼の反応を伺う。しかしどれだけ動かしても、ピクリとも動かず、ただ一点だけを見つめている。――さっき、ティカさんとメイリンちゃんが入って、出て行ったドアを。
「セ、セシアさん?」
その沈黙に耐え切れず声を上げると、彼はやっと動いて、顔の正面をこちらへ向けた。
「――口説く、ですか。 へぇ、それもなかなか……」
「へ? は? え、ええぇlっっ?!?!」
すっ、と動かされたその手は、彼の顔にかけてある黒い布をどかして、素顔を晒す。
見えたのは、色素の薄い茶色系の髪と、さも楽しそうに笑った表情。
そして……黄色の瞳。
「やっぱ口説くならこれは取らなきゃいけませんもんねぇ♪」
「えっ、あっ……っ」
生まれてこの方、こんなに異性に顔など近づけられた事は――た、たぶん2,3度しかない。 なので彼のその端正な顔を近づけられて、ちょっと……いや、かなり焦ったのだろう。
彼の鼻と私の鼻が触れるくらいの距離まで近づけられて――
バ チ ン ッ ッ
「ごふっ……」
――気が付いたら彼はテーブルとかなり熱い出会いをしていて、私の手は宙に浮いていた。
「あ、あははは……」
手が少しヒリヒリするのを感じながら、私は苦笑いをした。
「ひ、酷いですよエステアさん……」
「す、すみません……」
うるうると瞳に涙を浮かべながら言った彼に、私は素直に謝った。
そしてぎゅっ、と彼の腕を掴んで言う。
「大丈夫ですよ、セシアさん♪ このこともちゃんと「お話」にしてあげますから!」
「……結構です……」
かなり景気の良い音がしたので、やっぱり痛かったのだろう。
彼は紅くなった頬を押さえながら、そう返してきた。
* * *
そうして私のちょっとした気まぐれから、未来は変わっていく事になる。
私は薬師をする傍ら、彼の日記を元に「話」を書き、三日に一度、この家を訪れるようになり、彼は黒子のままで、日常を私に伝えてくれた。
新しいことを始めると、失敗することもあるが意外な発見を得られることもある。
――私の持論は、ちゃんと証明されたのだった。
「序章」 了
私は相変わらず文字と格闘する毎日を送っています。上手く繋がる時はいいのだけれど、なかなか繋がってくれずいつも完敗ですけどね。……貴方の話を聞いていた頃が懐かしいです。
あの時はその話を聞くだけでウズウズして、ペンを走らせるのが大変なくらいすぐに文章が出てきたのに。
メイリンは元気でしょうか?私が最後に見た時は10歳の誕生日を迎えた頃でしたよね。
――あれから3年。まだ早いかもしれませんが、メイリンの事だもの。もう立派な魔法使いになっていてもおかしくないですね。私にはよくわからない事ばかりでしたが、素質だけはあると思いましたから。
お師匠様も元気ですか?……相変わらずピーマン残してるのかしら?まぁ、あのピーマン嫌いをなくしたら彼が彼でなくなってしまうような気もするけどね。
あと少ししたら、お休みがいっぱい入るみたいです。
前と比べるとちょっと遠くなったけど、今回の休みは本当に長いので、久しぶりにそちらへお邪魔させて頂こうと思います。……いいですよね?
たぶん4月の中ごろにはそちらへ着けると思います。溜まっている原稿があるから荷物が重くなりそうなの。何となくそっちでやった方が捗るような気がしてね。
正確な日時が決まったらまた連絡しますので。……普通の格好で迎えに来てください。くれぐれも黒ずくめなんかで来ないでくださいね。前にあの格好で来て、警備隊に連れて行かれそうになったこと、覚えていますよね?あの時は本当に焦ったんですから。
それでは、次に会える日を楽しみにしています。
体に気をつけて、お仕事頑張ってくださいね。
――エステア=リーマイン
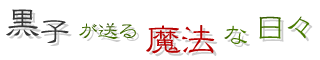
- 序章 「出会いは微妙でしたけど」 -
これは私の自論。でも、たぶん本当の事。
* * *
いつもは通ったりしない道を行くと、そこには家が建っていた。
大きくも、小さくもないものでかなり庶民的な造りのようだ。
薬草を探しに森へ入ったはいいが、最初の角をいつもと反対に曲がったのがいけなかったのだろうか?
実は……迷ってしまっていたようなのだ。
そして、半ばさ迷いながら歩いていた時、この家を見つけた。
屋根から飛び出ている煙突からは白い煙があがっている。という事は人が居る、という事なのだろう。
もう日も暮れる。
私は意を決して、その家の方へと向かっていった。
――ついでに言うと、探しに行った薬草はまだ手に入れていない。
家の近くまで行くと、美味しそうなシチュー(と思われる)の匂いが漂ってきた。匂いで判別するのは苦手……というか、ほとんど出来ないのだが何故かこのシチューはわかった。
これは私の好きなホワイトシチューの匂いだ。
少し意地汚いかもしれないが、私は鼻をひくひくとさせながらその匂いの元へと近づいていった。
あと3メートル……2メートル……1メートル――、少しずつ玄関のドアが近くなってくる。そして、あと少しでそのドアノブに手が届きそうになった時、その声が聞こえたのだ。
「あれ? お客さんですか?」
その声は……何処から聞こえたのか、わからなかった。
声がした瞬間、私は咄嗟に周りを見た。けれど……人影はない。
「お客さんのようですね……、いやはやご主人様の刺客かと思っちゃいましたよ」
姿は見えないのに声だけが聞こえる。その声は、すごく嬉しそうに笑っていた。
「いやぁ、うちのご主人様って結構刺客が多くって、全く世の中腐ってますよねぇ」
はっはっは、と遠くとも近くともとれない場所から笑い声が聞こえてくる。
辺りは一気に暗くなり、私の近くにも暗闇が忍びよ――……ん?
見間違いかもしれないが、私のすぐ傍まで来ていた暗闇が動いたような気がしたのだ。小さく、なのだが。それに……だんだんと近づいてくるのはわかるのだが、かなり早いペースだ。
私は思わず、身構えた。そして口を開ける。
「だ、誰なんですか!?」
するとその暗闇ははた、と立ち止まり――笑った。
「……そういえば、まだ紹介してませんでしたね〜」
そう言って光の下に出てきた人(男か女かは判別が出来なかった)は……やはり黒かった。
全身が黒ずくめ。――とか言うよりもこれは……。
私がその姿を見て驚いているのをまるっきり無視して、その人は手を差し出した。
「あ、どうも。黒子って言います」
「く……ろこ……?」
にこやかに差し出された手と、笑っているのだろう顔がある部分とを見比べた。
そして、(一応)手を握り返す。
「えぇ、黒子。楽しいですよ〜、気づかれないように人の後ろに立ってみたり。こっそりと後を付まわしたり」
……。
「あ、今こいつ変態だ、とか思いましたね?!思ったでしょう!」
――……何でわかったんだろう。心の中で小さく呟いたのは、まさしくソレだった。
「ふん、いいんです。皆この楽しさを知らないだけなんですから!」
ぷんすか、と怒っているのだろうか?顔が見えないので、声で判断するしかない。
彼は(ずっと“その人”と呼ぶのは大変なので仮に“彼”と呼ぶことにした)腕を組みながら何かを考えているようだった。しばらくしてその考え事が終わったのか、私の方をちらりと見て(だと思う)訊いてきた。
「ところで、貴方はどうしてこんなトコに? 辺鄙だし、人はめったに近づかないんですよ?」
そう言う彼に、私は事情を説明した。とどのつまり、薬草を探しに出て道に迷ったのだということを。
「なるほど、確かに普通は皆さんこっちの道には来ませんもんねぇ。あ、もしかして知りません?この家、化け物屋敷って言われてるんですよ」
まぁ、実際に化け物居るんであながち嘘とも言えないんですけどね、と彼はまた笑った。
「ば……けものが居るんですか……?」
思わず後ずさった。そういえば近所の人達がそんな事を話していたような気がする。
「あ、大丈夫ですよ。取って食いやしませんて」
「当たり前ですっ!!」
相変わらず、はっはっはと笑いながら言う彼に、私は声を上げた。
「だいたいっ……あなたは誰なんですか?! こんな所に黒子なんて必要ないでしょうっ?!」
すると彼は驚いて(だと思う)言った。
「あっ、心外ですねー。黒子っていうのは何処に居てもおかしくないと言われているのに」
「そんな事言われてるんですか……?」
「はっはっは、嘘に決まってるじゃありませんか」
――……こ、こいつ……!!
私がその言葉に怒ったのを見たのか、それとも元々こういう性格なのか、彼は思い出したように話題を巧妙にすり替えた。
「さて、もうすぐ夕食の時間ですね。あと少しでもシチューを放って置いたら大惨事になりそうです」
心配をしているような台詞。でも口調だけで判断すると全然、これっぽっちも心配しているように思えない。
「いやはや、別にあの家が火事になろうとどうでもいいんですがね。やっぱりシチューだけは守り抜きたいじゃないですか。僕、シチュー作るの上手いんですよ〜」
……“家<シチュー”の方程式を作る彼。――……一体、何なんだろう?
「どうです?もう遅いですし、良かったら一緒に食べます?」
そう言って彼は、親指を立てた手で後ろの家を指差した。……とは言っても、「黒子」が勝手にそんな事を決めてもいいのだろうか?どう思っても、「黒子」は家の主人じゃないような気がする。
「え、でも……」
言い淀む私に、彼はきょとんとして……でもすぐに笑って言った。
「あぁ、大丈夫ですよ。あの家の金握ってんのは僕ですから。ある意味最高権力者ですしね」
そうでなければあの人達、今頃飢え死にしてますってば、と手をはたはた振りながら続けた。
私はそんな彼にかなりな疑問を覚えながらも、軽く頷く。
「……そ、それじゃ……ご一緒させてください……」
「よし。 それじゃ、どうぞ。 ちっこい外見ですけど、中身は無意味に広いんですよー」
周囲もだんだんと暗くなってきて、その闇に溶け込むように存在する彼。私は彼の言葉に首を傾げながら、その後に続いた。
――近づくにつれ、シチューの匂いが増していった。
* * *
「馬鹿者! 何度言ったらわかるんだ。
火を出すときは右手を逆時計回りに2回転して印、だっつってるだろーが!!」
「んな説明初めて聞いたし。師匠、いくら年だからって急速にボケんのマジ困るんでやめてくださいー」
黒子に案内されて入った家からは、こんな会話が飛び出してきた。
「あ、あの……」
「はい?」
相変わらずどんな表情かわからない(まぁ、黒子だから仕方がない事なのだけど)彼に、私は恐る恐る話しかけた。
「……こっ、この声はどちら様で?」
大方予想はついているけれど、何となく外れていて欲しいなぁ、なんて思ってみる。
「あ、このクソ煩い馬鹿ダミ声ですか?」
けれども黒子は絶えず嬉しそうな声を出し、私の思っている事、ドンぴしゃな答えを返してくれた。
「“一応”この家のご主人様ですよ。 そしてもう一人はご主人様に弟子入りしている子です」
どっちも腐りきってますけどね〜、とあくまでにこやかに言い放つ。
……って、腐っても“ご主人様”なんじゃ。そう思うけれど、先ほどの彼の言葉『最高権力者』発言から考えるに。“ご主人様”なんて露ほども、いや、もしかすると“僕(しもべ)”くらいに思っているのかもしれない。
「な、なかなか賑やかなご家庭で……っ」
自分でもよくわかる、限りなく引きつった笑みでそう返した。
コンコンコン
「ティカさん、メイリン。 そろそろ食事にしますよー」
彼は罵声が飛びまくっていた部屋のドアとノックし、呼びかけた。そして慣れた手つきで液体入りのバケツを紐で吊るしている。――はい?
+ + +
「あぁ、わかった。 ったく、メイリン、後片付けしとくんだぞ!」
「何言ってんの、師匠ってば。 今日の片付け当番は師匠じゃないですか」
マジにボケなんですかい、とソプラノの声で毒舌は続く。
「何ぃ?! 師匠に向かってその口の聞き方は何だ! こらっ、メイリン待ちなさい!!」
今にも掴みかかろうとする“師匠”に向けて、メイリンはにっこり笑った。
そして、――右手を逆時計回りに2回転、そして印。
ボムッ
「んなあぁぁっっ?!?!」
「あ、ホントに炎だ」
師匠に向けて特大の炎を放ったと言うのに、術が成功した事しか頭に入らないらしい。後ろの方で服に移った炎を消すのに大奮闘してる師匠を他所にメイリンはドアを開けた。
ザッバーーンッッ
「……………………」
ガランッ カランッ ……
ドアを開けると上からざばーっ、その後には空っぽバケツがごろんごろん。
「あっはっは、そんな初歩的なモノに引っかかるなんて。メイリンらしくないですよ?」
どう考えてもコイツが仕掛けた、その罠(?)にメイリンは青筋を立てる。
「くぅーろーこー?!!!!」
可愛らしい顔がかなり怒っているのも気にせずに、黒子は動いた。
――手拍子1回、右手を時計回りに1回、十字を切って、最後に印。
ボボボボッ ボボムッ
「「んなあああぁぁぁぁっっっっ?!?!?!」」
黒子が火を放ったかと思うと、突然部屋が爆発した。……さっきのバケツの中身、油だったらしい。
「あつっ、あつあつあつあつあつつつ?!?!」
「はっ……、早く消化を! 水っ、水の呪文!!師匠ぉっ!!」
「水の呪文、水の呪文……って馬鹿、オレを何だと思ってるんだ!呪文なんかなくたってええぇああっつぅ!!」
+ + +
「……ご、ごめんなさい。やっぱり私帰った方がいいんじゃないかと思ったりなんかしたりするんですけど」
ドアの向こうは炎一色なのに、不思議に熱さは感じなかった。むしろ、寒い。
「え? あ、ダメですよ。今この森を生身の人間が一人で歩くと危険過ぎます」
「……そ、それってどういう――」
聞きたくないような気がかなりしたが、私は訊いてしまった。
彼はくすり、と笑うとドアを閉めながら答える。
「いやぁ、ここらへんってモンスターの巣窟なんですよね。と言っても、ほとんどご主人様が作った“メイリン用”のなんですが。 でもメイリンを襲うだけじゃないですから、ダメなんですよ」
そしてまた、ドアを開けた。
ドアの向こうの火はいつの間にか収まっており、中にはずぶぬれになった人達が居た。
「あれ、お二人とも随分と濡れてらっしゃる。 それじゃご飯の前にお風呂にしますか?」
いけしゃあしゃあと言い放つ彼を見て、私は思わず後ずさる。
……とんでもない所に来てしまったかもしれない、そう思ったからだった。
* * *
結局私はこの家に今晩だけお世話になることにした。……というか、お世話にならなきゃいけない状態に陥ったからなのだけど。もし大丈夫なんだったらすぐにでも逃げ出したい気がする。
「ちょっと黒子、聞いてよ!師匠ってばあたしの事馬鹿って言うんだよ? この天才なあたしを捕まえて、馬鹿!ねぇっ、信じられる?!」
「何言ってやがるっ!大体、オレはお前に才能があるだなんてカケラも思っていない!」
「――んー、まぁ、どうでもいいですけど。少しでも下に物零したらとりあえず一ヶ月ご飯抜きますからね」
こんな会話が、さっきからずっと続いているのだ。
ちなみに食事を始める前に私がここに来た理由と一緒に、紹介もしてもらっていた。
“師匠”と呼ばれている男性――私と同い年くらいかもしれない――はティカさんと言うらしい。珍しい水色の髪が印象的な人だ。 そしてその“お弟子さん”のメイリンちゃん。フルネームは「メイ=リンドネス」と言い、メイリンというのはニックネームだそう。年は今年で9つだと聞いた。
……外見的には二人ともとても良い部類に入る筈なんだけど、さっきからの会話で十二分にわかるこの口の悪さ。しかもその上を行く彼――黒子。
やっぱり、私はとんでもない所に来てしまったのかもしれない。
その匂いに釣られてやってきてしまったホワイトシチューを啜りながら、私はまた考えた。
「ごちそーさまでしたっ!」
パチンッ、と手を合わせてメイリンちゃんが言った。いつもそんな風に、可愛らしい声で可愛らしい事を言えばいいのに、と知り合って間もないのに思ってしまう。
「ごちそーさん。 さて、修行の続きだ。メイリン、来い」
メイリンちゃんのすぐ後に同じように食後の挨拶(?)をして立ち上がるティカさん。その表情は見るからに怒っていて、それに対するメイリンちゃんの顔はとても不機嫌そうだ。
「えーっ、今日の分はもう終わったじゃんか。師匠はちょっとしごき過ぎ!」
「これでもミライザに比べたらマシな方だ!ぐだぐだ言わずにさっさと来い」
そう言ってさっと手を振った。
すると何もない筈なのに、メイリンちゃんの体が浮き上がって、ティカさんの後を追いかけるように部屋から出て行った。勿論、というのか……メイリンちゃんは怒っていたようだけど。
二人が出て行った扉を見つめていると、横から彼が声をかけてきた。
「エステアさん♪ シチュー、どうでした?」
「あ、えぇ。 とても美味しかったです」
彼は黒子特有の被り物を口元が見えるくらいの所まで引き上げて食事をしていた。まぁ、そうしなければ物を食べることが出来ないから仕方がないのかもしれないけど……とことん、怪しい。
「それは良かったです。このシチューは自信作ですからね〜」
おかわりとか入ります?、とテーブルの真ん中に置いてある鍋を指差しながら訊いてくる。
私は首を横に振った。
「もうお腹いっぱいです。シチューもですけど、全部本当に美味しかったですから」
シチューの他に出されたのは、とても柔らかいパンとサラダ。それにフルーツジュースだった。本当にお世辞ではなく、美味しかった。
「そうですか。いやぁ、嬉しいですねぇ。いつもあの二人は人が一生懸命作ってるものに対して何も言ってくれないもんですから。 ――ただの栄養補給としか思ってないんです、あの馬鹿共は」
彼はちょっと悲しそうにして(あくまで、雰囲気だけど)肩を竦めた。
私はそれに笑うことも出来ず、ただ曖昧な返事を返した。
食事を終えた後、私は彼の後片付けを手伝うことにした。「お客様は座っててください」と言われたけれど、私は譲らなかった。というのも、“誰かと一緒に”後片付けをするという事が久しぶりで、嬉しかったからだ。
「すみませんねぇ。 それじゃ、僕が洗いますから、その布巾で拭いて貰えますか?」
「えぇ」
隅にかかっていた布巾をとって、彼の隣に並ぶ。暫くの間は私の元に食器は来ない。洗い終えた食器が来るまで私は彼の手元を見ていた。
外で見たときとほとんど同じような服装だったけど、今は腕まくりをしていて素肌が見えている。やっぱり“彼”は男だったようで、私よりも随分逞しい腕が水をうけていた。
その様子を見ながら、私はふと思いついた事があり、それを口にした。
「……そういえば、貴方の名前は何て言うんです?」
そう、さっきの紹介では彼の事は一切触れられなかったのだ。
「僕の名前、ですか? うーん、そうですねぇ……何でしたかねぇ」
「何でしたかねぇ……って、自分の名前でしょうっ!?」
すっとぼけた答えに、思わず声を大きくしてしまう。すると彼は手を止めてこっちを向いた。
「いやいや、嘘ですって。ちゃんと覚えてますよ……けど、そう簡単には教えられません♪」
えっへん、と何故か勝ち誇ったように言われて一瞬カチンと来る。
「……べっ、別に教えて貰わなくてもいいですけどっ。 何て呼べばいいかわからないから――」
本当に何故かわからないのだけど、一気に頬が熱くなる。私は若干紅くなっているだろう顔を隠すように、彼に背を向けた。彼は、驚いたようだった。
「っ……僕の呼び方、ですか。 ……はは、何だか嬉しいですね。 よし、それじゃ特別に問題です!」
「問題?」
「えぇ、問題です。 僕の名前を当ててみてください。あ、4択ですから成功率は25%ですよ」
私は変な事を言い出した彼の方に向き直った。彼はまた手を動かし始めた。
「その1、ケント。 その2、ライザ。 その3、セシア。 その4、スイカ」
さぁ、どれだと思います?彼は顔だけをこっちに向けてそう言った。
……ケント? ライザ? セシア? スイカ?
一つ一つを反復しながら顔の顔と見比べる。……何となく、その4だけは違うような気がした。何故ならそれを言った時に少しだけ笑ったから。となると、選択肢は3つに絞られる。
私は腕を組んで考えに考えたけど、どれも合っている様で、どれも外れている様で。全くわからなかったので、ふんふん♪と鼻歌を歌いながら洗い物をする彼の服の裾を引っ張った。
「ヒント……ください」
「ふむ、ヒントですか。……アルファベットで書くと、“E”の文字が入りますね」
アルファベットで“E”。と言う事は、ケントかセシア?
再び思考時間に入る。……そして、私はある事を考えた。
「今から私が名前を呼びますから、合ってても違っても返事をしてくださいね?」
そう言ってから、息を吸い込む。
「――ケントさん」
「はい♪」
反応は完璧にふざけたもの。……これではないのかもしれない。
「――ライザさん」
「はいはい」
選択肢には入っていないけれど、一応言ってみる。……うー、でも、これも違うような気がする。
「――セシアさん」
「はい?」
顔は見えないけど、明らかに面白がった声。
「――ス、スイカさん」
「……はいv」
だ、だめだ……余計にわからなくなっちゃった。
仕方が無いので、「もう適当に言うしかない!」と無理やり自分を納得させる。
そして適当に、一つの名前を口に出した。
「その3、セシアさんですよね?」
彼は一瞬手を止めて……、すぐに笑った。
「はっはっは、いやだなぁ。 何でわかったんですか?」
「えっ、本当に合ってるんですか!?」
驚いて言うと、彼は何も言わずに少し肩を竦めた。……その動作を見て、嫌な予感が胸を掠める。
「……もしかして、どの名前を言ってもそう言うつもりだったんじゃないでしょうね?」
「はっはっは、いや〜、わかっちゃいましたか〜♪」
彼は悪びれもせず、そう返してきた。あまりにさらりと言うものだから、私は怒ることも忘れただ呆れていた。けれどもよくよく考えるとやはり腹が立ってくるもので。
「何ですかそれ。 ……もう、いいですよ!勝手にセシアさんって呼びますからっ」
「えぇ、何とでもお呼びください。 エステアさん♪」
自分だけちゃんと名前を呼んでズルイ、と思ってしまうのは仕方のない事だろうか。
私はやっと洗い終わってやってきた皿を受け取ると、ちょっと乱暴に水滴を拭き取った。
「よし、これで終わりです!」
拭き終わった食器を食器棚へ戻し、私は深く頷いた。
「どうもありがとうございました。 おかげで今日はいつもより随分早く終わりましたよ」
後ろでは彼が同じように頷いているところだった。
後片付けも一通り終わり、私は夕食時と同じ席に腰を下ろした。
「本当に助かりましたよ。 エステアさん、いつもやってらっしゃるんですか?」
彼はまだキッチンの方に居て、ちょこちょこと色んな所を拭いているようだった。
「えぇ。 一人暮らしだから、どうしてもしなきゃならないんですよ……」
「一人暮らし?」
呟くように言ったのに、彼には聞こえていたらしい。手を止めて、訊き返してきた。私はその言葉にしばし沈黙した後、ウーンと唸りながら答えた。
「ほら、この森の麓に青い屋根の家があるでしょう? 私、そこで暮らしてるんです」
彼が知っているとは限らないけど、私の家はどこかへ出かけるには必ず通らなければならない道の脇に建っているから、もしかしたらと思ってそう言ってみる。
すると彼はぽん、と手を叩いた。
「あぁ! ってことは、エステアさんはイウラ先生の娘さんですか?」
「父を知ってるんですか?」
家の場所はともかくも、まさか父の名前が出てくるとは思わず。驚いて彼の方を見る。
「勿論ですよ。 いやぁ、僕とした事が、“リーマイン”っていうので気づくべきでしたね……」
そう言いながら、こっちへやってきて、椅子に座った。
「そうですか……あのイウラ先生の娘さん――でも、一人暮らしって……先生はどうされたんですか?」
……。
何も知らないような口調に、一瞬頭が真っ白になる。
「父は……両親は亡くなりました。 一年ほど前ですけど」
かろうじて出した声の後に頭に浮かんだのは、思い出したくも無い光景で。私は思わず両手で顔の脇を抑える。 何とかそのイメージを消そうとするけれど、そうすればするほど、それは鮮明になっていった。
青ざめて戻らない顔色、衰えていく体、それでも微笑う表情。
あんなに早く逝ってしまうなんて、あんなに頑張ってたのに……なんでっ……。
「……テアさん、……エステアさんっっ!!!」
「え……?」
頭を抱えていた腕を彼に掴まれる。
私は顔をあげた。
「――すみません、僕知らなくて……本当にすみません……」
謝ってくる彼に私は首を振る。そして離してくれ、というようにそっと掴まれていた腕を動かした。 けれど彼はそれを離さず、とても悲しそうに言った。
「謝りますから、――泣かないでください……」
私の瞳からは、いつの間にか大粒の涙が零れていた。
* * *
「……大丈夫ですか?」
コトン、と湯気のたつ紅茶が入っているカップを置きながら、そう訊かれた。
「えぇ。 私の方こそすみません、いい加減慣れなきゃいけないのに……」
彼はもう一つのカップを自分の手元に残したまま、向かいの席に座った。
「別に慣れなくてもいいですよ。 ……居なくなるのは、寂しいことですから」
何処か悟ったような口調に少しだけ疑問を覚えたけれど、私は「そうですね」と呟き返すだけにした。
暫くは、お互いが紅茶を飲む音と時計が進む音だけが聞こえていた。
けれどずっとそんな気まずい雰囲気のままでいるわけにもいかない。私は、意を決して、声をかけた。
「あ、あのっ」
「あの……」
全く同時に、彼も声を出した。
「あああっ、いえっ、そちらからどうぞ!!」
「い、いえ――……やっぱり僕からいかせてもらいますね♪」
なんだそりゃ。最初の方はこっちに譲るような事を言おうとしていたんだろうに。
何だかおかしくなって、思わず笑ってしまった。
すると彼も笑って、「笑ってくれましたね。良かった」と嬉しそうな声で言った。
「あの、さっきの話を蒸し返すようで悪いんですが……エステアさんは今、何をやってらっしゃるんです?」
“さっきの”というのは、父さんの事だろう。ということは、今の……仕事の事?
「両親の意思を継いで、薬師をやっています」
そう、母さんは本業じゃなかったけれど、父さんは薬師をしていた。薬師とはとどのつまり、「薬を調合する人」だ。そしてそれを村の人や、町の医者に売っていた。
「と言う事はもしかして、今日森に居たのも……薬草を取りに来ていたんですか?」
「はい、この森は昔から貴重な物が多いですから」
紅茶を飲みながらそう返す。
「でも……、それなら何であんな所に居たんです?」
こっち側は危ないばかりで何も無いんですよ?、と更に付け加えられ、私は押し黙る。
そしてちらり、と視線を彼の方へ向けた。
「……笑い、ません?」
「? はい、笑いませんよ」
私の言葉に首を傾げる彼を見て、言おうかどうか迷う。しかし此処で「やっぱりや〜めた」なんて言っても納得して貰えないような気もする。
私はかなり小さな声で、理由〈わけ〉を話した。
「――いつもと違う道に行ったら、いつもと違う“何か”が見つかるかと思ったんです」
テーブルに肘をつき、顔の前で手を絡める。
「違う“何か”を見つけたら、それが違う世界に招待してくれそうな気がして。
そんな風に考えていたら、いつの間にか違う道を選んでたんです」
我ながらかなり夢を見ている発言だと思う。けれど本当の事だったから、自然と口に出来た。
そして、自分の思ってることがちゃんと言えた、と、ある意味誇らしい気持ちで彼を見ると……
「……ぷっ。 あは、あは、あはははははははっっっっ!!!」
……思いきり、笑われた。
「わ、わ、笑わないって言ったじゃないですかっっ!!!」
「あ、いやっ、すいませんっ。 でもおかしくて……っあはははっ」
ぶちっ
笑わない、と言ったくせにこの爆笑。幾ら温厚な私だって腹が立つ。 頭の奥で何かがキレたような音を聞きながら、私は無意識に立ち上がって彼の方へと歩み寄った。
いきなり立ち上がって、しかも寄ってきたのが怖かったのだろうか。彼は突然笑いを止めると、弁解をするように両手を前に出した。
「え、あ、いや、違うんですよっ」
「なぁーにぃーがぁー、違うんですかっ! セシアさんの馬鹿ぁっ!!」
ぽかぽかぽか、とそれほど強くない力で叩く。
彼はそれを受け止めながら、また、違うんです、と言った。
「エステアさんの事を笑ったんじゃなくて――昔、同じ事を言ってたヤツの事を思い出したんですよ! それでその時の事を思い出して、笑ってたんですっ」
ピタッ
彼が捲くし立てるように言った言葉に、一瞬手を止める。
「……ホントですか?」
「ホントです!」
訝しげな表情でそう訊くと、間髪入れずに答えが返ってきた。
その雰囲気(生憎表情はわからないので)が本当っぽかったので、私は手を下ろして、元の席に戻った。
「それにしても、エステアさんってお話が好きな方なんですねぇ」
「……また笑うつもりでしょう?」
「まさかぁ! それにさっきのは違うって言ったじゃないですか」
「セシアさんの言い方だと、いまいち信用出来ませんっ」
今度は別の意味での笑い(である事を願う)と共に言ってきた言葉に私はツンとして返す。
そんな私に、彼は笑って
「仕方ないですねぇ。 それじゃとっておきの物を見せてあげましょう♪」
と言って立ち上がった。
彼が向かった先はキッチンの冷蔵庫の横にある棚。一冊の本?……を取り出した。
「これ、何だと思います?」
「……さぁ? 家計簿?」
思ったままの事を口に出すと、彼は少しガクッときたようだ。
「なんで僕が家計簿なんてつけなきゃならないんですか……日記ですよ、日記!!」
「日記? セシアさんは日記をつける方なんですか」
それを持って元の席に戻ってきた彼にそう声をかける。
「えぇ、長い人生ですからね。 一応何があったのかは把握しておかないと、って思いまして」
パラパラ、と随分分厚いソレを捲っていく。
私はその様子を見ながら訊いた。
「――それがどう、とっておきの物なんです?」
彼はおもむろにソレを閉じ、私の方へ差し出すとこう言った。
「僕の日記を見て、物語、書いてみませんか?」
* * *
「……はい?」
差し出された、そのままの格好で私は思わず声をあげた。
「いや、だから、お話を書いてみませんか? って言ってるんですけど」
最初の言葉とは少しだけ変えて、言ってくる。
「え、ちょっと待ってください。 ……何でお話、なんですか? っていうか何で私?」
「エステアさん、お話考えるの好きなんですよね。 だから、もし良かったらどうかな〜、って」
まだ混乱する私を他所に、彼は話し始める。
「ちょっと前から考えてたんですよ。僕はこうしてあの馬鹿共を養ってやってるんですが、どうも刺激に欠ける生活なんですよね〜。なので、毎日の終わりに日記を書いても何だかつまらなくて。
でも、ですね。ふと思ったんです、この僕等の日常を誰かが「話」にしてくれないかな、って。 僕は日記ならまだしも、そういう物を書くのが苦手だから……ね、ダメですか?」
ずいっ、と顔を近づけられ……一瞬だけど、その黒い布の向こうに黄色い瞳が見えたような気がした。
私は本当に話を考えるのは好きだったし、彼の話は面白いと思った。そして何より、一瞬布越しに見えた表情を見て、私はすぐに首を縦に振った。
彼はそれを承諾の印と、とって、「良かった」と呟いた。
そして日記を改めて私の方へと差し出して、言った。
「僕の一人称で語られて、エステアさんはそれを僕から聞いた話、という事で書いていくんです。
物語の登場人物はとりあえず4人。 語りべの“僕”に、メイリンとティカさん。そしてエステアさん。他は――時々出てくるイレギュラーな人達、とか」
嬉しそうに話す声に、こっちまで何だか嬉しくなってしまう。
「楽しそうですね」
そう言うと、彼は少しだけ声を抑えてこう返した。
「えぇ、楽しいですよ。 だから……それを残してくれる人をずっと探してたんです」
そして、私の手をとり、呟くように付け足す。
「……やっと、見つけました。きっと、エステアさんが今日違う道を行ったのも運命だったんで――」
バタンッッ
「師匠っ!! 黒子がエステアお姉ちゃんを口説いてるよ! 早くっ、ほらっっ!!!」
「馬鹿、メイリン!こういうのは影からそっと見なくちゃいけないんだぞ! わかったら早くドアを閉めなさい!」
パタン
……。
…………。
え、えぇ……っと……。
未だに握られているその手を少し動かして彼の反応を伺う。しかしどれだけ動かしても、ピクリとも動かず、ただ一点だけを見つめている。――さっき、ティカさんとメイリンちゃんが入って、出て行ったドアを。
「セ、セシアさん?」
その沈黙に耐え切れず声を上げると、彼はやっと動いて、顔の正面をこちらへ向けた。
「――口説く、ですか。 へぇ、それもなかなか……」
「へ? は? え、ええぇlっっ?!?!」
すっ、と動かされたその手は、彼の顔にかけてある黒い布をどかして、素顔を晒す。
見えたのは、色素の薄い茶色系の髪と、さも楽しそうに笑った表情。
そして……黄色の瞳。
「やっぱ口説くならこれは取らなきゃいけませんもんねぇ♪」
「えっ、あっ……っ」
生まれてこの方、こんなに異性に顔など近づけられた事は――た、たぶん2,3度しかない。 なので彼のその端正な顔を近づけられて、ちょっと……いや、かなり焦ったのだろう。
彼の鼻と私の鼻が触れるくらいの距離まで近づけられて――
バ チ ン ッ ッ
「ごふっ……」
――気が付いたら彼はテーブルとかなり熱い出会いをしていて、私の手は宙に浮いていた。
「あ、あははは……」
手が少しヒリヒリするのを感じながら、私は苦笑いをした。
「ひ、酷いですよエステアさん……」
「す、すみません……」
うるうると瞳に涙を浮かべながら言った彼に、私は素直に謝った。
そしてぎゅっ、と彼の腕を掴んで言う。
「大丈夫ですよ、セシアさん♪ このこともちゃんと「お話」にしてあげますから!」
「……結構です……」
かなり景気の良い音がしたので、やっぱり痛かったのだろう。
彼は紅くなった頬を押さえながら、そう返してきた。
* * *
そうして私のちょっとした気まぐれから、未来は変わっていく事になる。
私は薬師をする傍ら、彼の日記を元に「話」を書き、三日に一度、この家を訪れるようになり、彼は黒子のままで、日常を私に伝えてくれた。
新しいことを始めると、失敗することもあるが意外な発見を得られることもある。
――私の持論は、ちゃんと証明されたのだった。
「序章」 了